〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301
電話での受付:15:00~20:00
定休日:日曜日
生徒さんへ 〜親たちはなぜ「勉強しろ」というのか〜 あなたの「将来」とのかかわり その1 2016/12/01
12月になりました。
受験生はもうすぐ入試本番が待っています。
気を引き締めて臨みたいものです。
さて、今日は生徒さんたちに、親たちはなぜ「勉強しろ」というのかを話してみたいと思います。
生徒さんは自らの意志に関係なく、この世に生を受けます。
そしたら有無を言わせず、義務教育ということで学校に通うようになります。
お勉強が得意な生徒さんもいれば、苦手な生徒さんもいます。
苦手な生徒さんにとってみれば、大変なこと、この上ないものがあります。
よって勉強から遠ざかってしまう人もいます。
わたしが生徒さんに「そもそもなぜ勉強しなければいけないと思いますか?」と尋ねると、かなり多くの生徒さんが「将来のため」と答えます。
「将来、困らないようにするため」
「将来、いろんな資格を取って、それを生かすようにするため」
など、「将来」というキーワードを口にします。
それはもちろん正しい答えです。
では、今の勉強の成果が、将来、どのように自分の生活とかかわるようになってくるか、ということになると、生徒さんは十分な知識がありません。
実体験がないので、それも当然のことです。
その辺りのことを、周りの大人たちというのは、あまり具体的に語りません。
しかし、以下、お話しすることは、社会経験のある大人ならば、誰でも知っている「常識」です。
前置きが長くなりましたが、それをわたしの経験に基づいて、お話しすることにします。
(次回に続きます)
生徒さんへ 〜親たちはなぜ「勉強しろ」というのか〜 あなたの「将来」とのかかわり その2 2016/12/02
(前回の続きです)
わたしは高校の同級会で、「昔、シャカリキになってやった受験勉強、役に立っているか?」と尋ねたことがあります。
そこに集ったのは、医師、大学教授など学校の先生、キャリアと言われる霞が関の官僚・宮城県庁などの公務員、名の知れた会社で部長とか、課長とかいう職についている人たちばかりです。
彼らに質問をぶつけると、以下のような答えが返ってきました。
「まあ、役に立っているといえば、立ってるかな。いろんな試験もあったしね。その基礎になってる」
「そんなに役に立ってないかな。数学でやった微分・積分なんて使ったこともないなあ」
いろいろです。
そんな彼らですが、「役に立ったのか、立たなかったのかよく分からないような」受験勉強をやって後悔している、という人は誰もいませんでした。
またわたしが会社勤めをした経験から申すと、上司や同僚がどういう学歴を持っているのか、というのは、全員の知るところとなっていました。
「今度入社した〇〇さんは、〇〇大卒で.....」
「〇〇部長は、〇〇高卒で、そのままずっと今までうちの会社なんだ.....」
ということがちょくちょく話題として出てきました。
そして学歴はその人物が有能であるか、そうでないかを測る、材料の一つになっていました。
以上の例が「なぜ親たちは『勉強しろ』というのか」という問いに対する答えの一つになっています。
(次回に続きます)
生徒さんへ 〜親たちはなぜ「勉強しろ」というのか〜 あなたの「将来」とのかかわり その3 2016/12/03
(前回の続きです)
仕事の上で大切な給料に関して言えば、ほぼ全員が何らかの形で社会に出る20代中盤までは、学歴の差で収入が大きく変わってくるということはあまりありません。
30代に入って、徐々に差がつき始めます。
そして30代半ば〜40くらいになると、目に見えるほどの差になって現れます。
「昔、同級生だった〇〇は、しっかりした会社に就職して、結婚して、2人の子供がいて.....
なのに自分は、派遣社員で、自分の生活がやっとで、家庭を持つなんて夢のまた夢」
と思っている大人はたくさんいます。
今、「勉強もしたくないし、かといって、就きたい仕事も、将来やりたいこともない」という生徒さんは、仮に「自分の生活だけでやっと.....」という職業に就いた後、「同級生だった〇〇」との差に、耐えることができるかどうか、ということをじっくり考えてみることをお勧めします。
しかも「自分の生活だけでやっと.....」というのは、その年齢になってみて初めて分かることなのです。
とはいえ、学歴だけがすべてではありません。
高学歴であるということは、「ゴールまで、何がしかのアドバンテージを手にしている」ということだけです。
言い換えると、他人より1分2分、早くスタートできる権利を持っているというだけです。
ですから、学歴は持っていなくても、商才を生かせれば、並みいる高学歴者をアゴで使うことも可能です(笑)
高学歴を「人生のゴール」と勘違いしてしまうと、大変な目に遭います。
生徒さん、どうでしょう?
参考になりましたか?
ひとつの教室に6学年の差! 〜公立小中学校での「国語力」の「圧倒的な差」〜 その1 2016/12/04
突然ですが、ある教室で、小学5年生から高校1年生の生徒が、一堂に会して、一人の先生の授業を聞いているという場面を想像してみてください。
「いくら何でも、小学5年生から高校1年生の生徒が、一人の先生の授業を聞くなんてあり得ない」と感じるかもしれません。
しかしわたしに言わせると、この「あり得ない」状況が、公立小中学校の授業そのものなのです。
そう判断する理由というのは、生徒さんの「国語力の差」です。
「国語力の差」というのが、何を意味するのか、議論の余地はありますが、ここでは「単語力、読解力、表現力」とします。
わたしが判断するに、どんなに少なく見積もっても、ひとつの教室に6学年の差が存在します。
つまり、中学1年の教室であれば、小学5年生から高校1年生までいるということです。
その差というのは圧倒的であり、本人の努力によって容易に克服できるものではないと考えています。
分かりやすい例えを出すと、わたしと福山雅治さんや木村拓哉さんとの「見た目の差」です(笑)
越えようにも越えられない壁があるということです。
普段、ご父兄は、特段考えることなく子息を学校に通わせていると思います。
その教室の中では想像以上に「極めて大きな差」があるということをご理解ください。
(次回に続きます)
ひとつの教室に6学年の差! 〜公立小中学校での「国語力」の「圧倒的な差」〜 その2 2016/12/05
(前回の続きです)
では、具体的にどれほどの差なのかを申し上げることにいたします。
先日、わたしは、仙台一高を志望している中3の生徒さんに、国語の現代文のセンター試験を解いてもらったことがあります。
センター試験とは、申すまでもなく、高校3年生が大学受験のために受けるものです。
そこでその生徒さんが得た点数が、現代文100点に対し、64点です。
これがどれほどの点数かといえば、ほぼ「平均点」となります。
センター試験は高3生全員が受けるわけではありませんから、なかなかの点数であると判断できます。
よってこの生徒さんは、「高校3年生の平均ちょい上の国語力」を持っていると申してもいいでしょう。
ちなみに仙台二高の2年生の生徒さんに同じ問題を解いてもらったところ、100点中95点で、まあ妥当なところです。
以上を見てわかることは、ナンバースクールのようなところを目指すのであれば、少なくとも「平均より3学年上」の国語力を持ってなければ、入学後の学習には太刀打ちできないということです。
逆に「いくら努力しても、平均を超えることができない」という生徒さんならば、持っている国語力が平均以下であるとお察しください。
それは残念なことに容易に変えることはできません。
(次回に続きます)
ひとつの教室に6学年の差! 〜公立小中学校での「国語力」の「圧倒的な差」〜 その3 2016/12/06
(前回の続きです)
国語力が、平均に達していないということは、受容できるものが、平均的な生徒さん以上になることはできません。
例えば、今、中学2年生の理科では、天気の仕組みを学びます。
その際、冬になると窓が結露する現象を扱い、「飽和水蒸気量」「露点」という用語が出てきます。
ここが分からないという中2生が結構います。
こんな具合です。
生徒さん: あの〜、飽和水蒸気量とか露点のところがよく分からないんですが.....
菊池: そうですか。じゃあ、確認しますが、飽和水蒸気量の「飽和」って、どういう意味ですか?
生徒さん: え..... 何だろう?
菊池: じゃあ、「飽和」の「飽」の字は訓読みで何と読みますか?
生徒さん: 分かりません。
菊池: そこが分かっていないから、この仕組みが分からないんです。
「飽和」の「飽」は訓読みすると「あきる」って読むんです。
そういうわけで、「飽和」っていうのは、「おなかいっぱい」っていう意味です。
だから「飽和水蒸気量」っていうのは、ある温度の空気が抱えることのできる水蒸気量の限界っていう意味なんです。
生徒さん: へえ〜 そうなんですか〜
だいたい毎年1回はこのやり取りをやります。
それも1回説明しただけでは足りずに、何度か同じ説明をしないと分かってもらえない場合も出てきます。
国語力がしっかりしている生徒さんならば、このようなやり取りをすることはありません。
(次回に続きます)
ひとつの教室に6学年の差! 〜公立小中学校での「国語力」の「圧倒的な差」〜 その4 2016/12/07
(前回の続きです)
ここで理解の決め手となっているのは、生徒さんの単語力です。
「飽和水蒸気量」という仕組みを理解するのに、「飽和」という意味を理解せずして、全体の仕組みを理解することはできません。
以上は一例にすぎませんが、国語力が追い付いていないということは、上記のようなことがあらゆる科目全般にわたって見られるということです。
また単語力の不足は、聞き取りの力、そしてそれを理解してメモを取る力にもつながります。
これはわたしのことですが、英語を聞いていて、「あれ、ここ、何て言ってるんだろう?」ということはちょくちょくあります。
その部分というのは、わたしが知らない、またはよく理解していない単語や熟語です。
「あれ、何て言う意味なんだろうな?」と一瞬考えているうちに、会話はどんどん先に進みます。
そして理解度が下がります。
また英語の例を出さなくとも、職場で「聞いたことがない会社」「聞いたことがない珍名さん」から電話がかかってきて、「すみませんが、どちらさまでしょうか? もう一度おっしゃっていただけますか?」というようなことはあります。
知らない単語は聞き取れません。
これと同様のことが、上記のような生徒さんに起きています。
しかもかなりの頻度で、毎日です。
その生徒さんにとっては、そういう状態が慣れっこになってしまっています。
「一つの教室」の現状は、「かくも大きな差」が生じていることをご理解ください。
部活と勉強 〜頑張れない人って、やっぱり.....〜 その1 2016/12/08
先日、高校2年生の生徒さんと、部活と勉強との関係について、話したことがあります。
ちなみにその生徒さんの所属している学校は、スポーツの盛んな某私立高校です。
彼はそこで日々スポーツに汗を流しています。
こんな会話でした。
菊池: 勉強とスポーツの両立ってかなり大変だと思うんですが、勉強とスポーツって関係あると思いますか?
生徒さん: どうなんでしょうか。あんまり詳しくは分かんないんですが.....
菊池: じゃあ、質問を変えましょうか。
チームメイトで「うまいなあ」とか「練習熱心だなあ」っていう人は、勉強もそれなりにやってると思いますか?
それともあんまり関係はないですか?
生徒さん: ああ、それは関係あると思います。
練習を一生懸命するヤツって、勉強もそれなりにやってますね。
あんまり赤点とか取りません。
逆に練習をあんまりマジメにやらないっていう人は、勉強もちゃんとやらないですね。
遊ぶこととか、女の子とどう付き合うかとか、そういうことばっかり考えてます。
うちの学校、そんなに勉強は厳しいほうではないと思うんですが、マジメにやらないヤツは赤点が多くて.....
菊池: 赤点が多いとか、マジメに勉強をやってないっていうのは、どうやって分かるんですか?
生徒さん: 「こいつ、勉強やってない」っていうのは、何となく分かるもんですし、それからうちの部は赤点とると、何日間か練習に参加させてもらえないんで.....
菊池: そうなんですか。
いろいろと厳しいんですね。
(次回に続きます)
部活と勉強 〜頑張れない人って、やっぱり.....〜 その2 2016/12/09
(前回の続きです)
上記の会話からはいろいろなことが見えてきます。
部活と勉強の両立というのは、中高校生にとって、永遠の課題です。
わたしはこれまで、「部活を頑張りすぎて、勉強が疎かになってしまった」という生徒さんを数多く見てきました。
部活動をどれだけ頑張っているかというのは、客観的に測る物差しがないので、判断は難しいところです。
わたしが見る限り、「部活動をマジメにやらない生徒さんは、勉強もマジメに取り組まない傾向が強い」ということです。
部活を頑張りすぎて、勉強が疎かになるという生徒さんの場合、勉強がしっかりできる環境になれば、指導もスムーズです。
逆に部活をマジメに取り組まないという生徒さんは、勉強でも同じです。
「部活が忙しくて、課題ができませんでした.....」という言葉を口にするのが、このタイプの人です。
体育の成績も今一つだったりします。
わたしの生徒さんで、内申がオール5またはそれに近い人というのは、若干名います。
彼らを見ていて感じるのは、「何事にもマジメに取り組んでいる」ということです。
もちろん、学校の成績というのは、いろんな要素から評価されているのですが、中途半端な生徒さんというのは、部活でも勉強でもそうなのです。
「読書好き」なのに「読解力がイマイチ」という生徒さん その1 2016/12/10
先日書いた「ひとつの教室に6学年の差!」という題のコラムは、ご父兄の方々から通常以上に反響がありました。
いただいたお言葉の大半は、「そんなに差があるものなのか.....」ということです。
実際の指導に当たっているわたしに言わせると、ああいうふうにでも考えない限り、生徒さんの「差」というものを的確に説明できません。
閑話休題。
今回は、生徒さんの国語力に関して、先般の続編というべきものを書いてみます。
「国語力を高めるには、読書をする」というのは、よく言われることです。
わたしもこれには全く同感です。
しかしその一方で、「読書をすれば国語力が高まるのか」と言われると、「必ずしもそうではない」というふうに考えています。
意外なことに、「自分は読書が好き」といいながら、文章の読解力が芳しくないという生徒さんが見受けられます。
そういう生徒さんのパターンは次のようなものです。
1.読んでいる本は、小説や物語、アニメや映画を題材にしたライトノベルなどにほぼ限定されている。
2.その学年であれば通常知っているような常識的なことを知らない。
3.男子よりも女子にその傾向がある。
上記以外にも、「読書好きと自認しながら、実は文章に触れている量が少ない」という要素もあるように考えています。
(次回に続きます)
「読書好き」なのに「読解力がイマイチ」という生徒さん その2 2016/12/11
(前回の続きです)
ほんとうに読書をしているのかどうかということは、客観的に確かめようがありません。
あくまで自己申告です。
そうした中で、「読書をしている」と言っても、随分と差があるのではないでしょうか。
それから単語力に関して申し上げると、読解力が低い生徒さんは、理解できる単語の数は少ないです。
例外はありません。
とするなら、そういう生徒さんが「読書をしている」と言っても、理解できない単語が多いはずです。
「何となく読んだ気になっている」
「感覚で読んでいる」
「実は内容が頭に入っていない」
ということがあり得ます。
これが楽しみのための読書であれば、問題がありません。
何も読まないよりは、なにがしかの活字を目で追うほうがいいでしょう。
しかし学習という観点から見てしまうと、そういう読書は、あまり効率的でないということになります。
となれば、そういう生徒さんは、平均的な読解力を得ようとすれば、読解力のある生徒さんの数倍は読まなくてはならない勘定になります。
読解力のある生徒さんならば、それなりの読書をしているのが普通です。
そのため、知っている単語が少ないという生徒さんは、平均的な生徒さんに追いついていくというのは、かなり難しくなります。
(次回に続きます)
「読書好き」なのに「読解力がイマイチ」という生徒さん その3 2016/12/12
(前回の続きです)
以上のようなことがあるため、耳から入ってくる情報、学校での授業が生かしきれないことは、「その学年であれば、通常知っているという常識的なことを知らない、ということにつながります。
「その学年であれば、通常知っているという常識的なこと」というのは、例えば、こういうことです。
太陽はどちらから昇るか.....
地図上で東西南北は上下左右どちらの方向になるか.....
氷は何度で水になるのか.....
宮城県は日本地図だと、どのあたりに位置するのか.....
こういったようなことは、中学生段階ならば知っていてほしいことです。
そういうところの知識に乏しい生徒さんというのは、意外にいます。
普段はそれが直接問われるわけではないので、表面化することは少ないです。
しかしわたしが指導をしている際、「どこが分からないのか」をたどっていくと、こういった知識がなくて、文章の意味が取れていないという生徒さんはいます。
学年が進めば進むほど、読解力が必要な文章に接する機会が多くなります。
それは何も国語だけではありません。
他の教科もおしなべてそうです。
さらに、国語の読解ということに関して言えば、その学年で求められるいろんな知識がないと、文章をしっかり理解することは困難になります。
例えば、国語あるいは英語の長文問題の題材としてよく出てくる環境問題は、理科や社会の知識が必要です。
それが分からないと、いくら単語力があっても、文章の中身が理解できません。
「学習に生かす読書」は「趣味としての読書」と、ズレがある、ということをご理解ください。
高校受験用「宮城ぜんけん模試」取り扱いを始めます 2016/12/13
高校受験用の模擬試験として昨年より実施されております「宮城ぜんけん模試」の取り扱いを始めることになりました。
これまで中学生向けの高校受験用模擬試験と言いますと、当地では「みやぎ模試」が圧倒的シェアを占めています。
「宮城ぜんけん模試」は、それに対抗する形で昨年から実施されています。
この「宮城ぜんけん模試」の最大の特長は、「通信票の評定が加味されて判定が出る」ということです。
「みやぎ模試」は純粋に模試の成績だけから判定を割り出しています。
よって「宮城ぜんけん模試」のほうが、より入試本番に近くなっています。
わたしの生徒さんの場合は、学習塾と併用しているご家庭が何軒かあり、そちらでは「みやぎ模試」をすでに受験しています。
それと併せて受験をしてみると、より「正確な判定」が出てくるものと思います。
ご検討ください。
なお以前、弊コラムにて「宮城ぜんけん模試」のことを記しております。
こちらもご参考にしてください。
<実施要項>
◎中3生
平成29年1月7日(土)
受付時間 8:30〜8:50
試験時間 9:05〜15:00
場所:TKPガーデンシティ仙台勾当台TKPガーデンシティ仙台勾当台3Fホール7
(仙台市青葉区国分町3丁目6番1号仙台パークビル)
費用:
4,000円
申し込みの締め切り:
12月22日まで
◎中1,2,3生
平成28年1月28日(土)
その他の要項については、判明次第ご連絡いたします。
☆受験の手続きについては、菊池のほうで取りまとめます。
受験は他の一般の方との会場受験になります。
詳細については、こちらをご覧ください。
なお、本件につきましては、すでに1件、お申し込みをいただいております。
わたしが担当するご家庭には、別途改めてご連絡するようにいたします。
中学生ならびに中学生をお持ちのご父兄様へ 〜高校中退をしないために〜 その1 2016/12/14
中3生は本格的に受験モードに突入済みです。
そのような折に、「何でこんな話題を?」といぶかしがる方もいらっしゃることでしょう。
しかし今回は、このような折ゆえに、あえて高校中退に関して取り上げてみます。
高校はご存じの通り、義務教育ではありません。
それゆえ入学のためには試験があります。
しかし入学したはいいが、様々な理由で中途退学する人も少なくありません。
文部科学省が発表している数字によると、平成25年の統計で、全国平均の中退率は1.7%です。
宮城県の高校生63,520人のうち、中退率は1.8%です。
これは高校生の55人に1人は辞めている計算になります。
そして退学者の人数は1,136人です。
1.8%と率だけを聞くと大したことがなさそうですが、県内では高校を途中でやめている人が毎年1,000人以上いるのです。
これは大きな数字なのではないでしょうか?
またちょっと古い数字にはなりますが、平成23年に内閣府は高校中退者の意識調査を行っています。
その数字によると、中退した理由は、複数回答で、上位から以下のようになっています。
1位 欠席や欠時がたまって進級できそうもなかったから 54.9%
2位 校則など校風が合わなかったから 52.0%
3位 勉強が分からなかったから 48.6%
4位 人間関係がうまくいかなかったから 46.3%
この数字をどうお考えになるでしょうか?
(次回に続きます)
中学生ならびに中学生をお持ちのご父兄様へ 〜高校中退をしないために〜 その2 2016/12/15
(前回の続きです)
上記の数字について、以下、わたしの考えを述べます。
中退理由について、大きなものは、「学習面での遅れ」と「人間関係」に集約されています。
なぜ、欠席や欠時がたまってしまったのかと言えば、学校の授業についていけなくなったというのが、最大の要因と思われます。
高校は、中学校に比べて、通学時間が長くなるという人がほとんどです。
通学時間について、中学校ほどの「お手軽さ」はなくなってしまいます。
となれば、勉強についていけなくなってしまえば、どうしても学校は遠のいてしまいます。
高校には赤点という制度があり、一定以上の点数を定期試験で取らなければ、留年ということになります。
建前上はそうですが、実際には、追試験などで救済されることがほとんどです。
しかしそもそも欠席や欠時が多ければ、救済のしようがありません。
留年するというのも一つの手ではありましょう。
ただそうは言ってもも、周りが年下ばかりとなってしまうと、そういう環境で過ごすのは、それだけでなかなか耐えられることではありません。
ただでさえ、学校は遠くなってしまっていますから、そうなると自然と中退ということになります。
人間関係についても、登校しないことで、普通に通学している同級生との心理的な距離がギクシャクしてしまうということは大いに考えられます。
(次回に続きます)
中学生ならびに中学生をお持ちのご父兄様へ 〜高校中退をしないために〜 その3 2016/12/16
(前回の続きです)
高校中退者については、現在、様々な受け皿が用意されています。
これをお読みの方が一番知りたいこととは、高校中退が就職するときマイナスになってしまうのか、ということでしょう。
これに対してのわたしの答えは、就く職業にもよりますが、中退せずに卒業した人と比べてしまうと、どうしてもマイナス要因になってしまうことは否めません。
それはなぜかと言えば、こういうことです。
「欠席や欠時がたまって進級できそうもない」「校則など校風が合わない」という理由で、高校を中退した人を、企業の採用者はどう考えるでしょうか?
「この人は、雇っても欠勤が多いのではないか?」
「社風と合わないと称して、会社を簡単に辞めてしまうのではないか?」
と考えてしまうのではないでしょうか?
学校と違って、企業は利益を出さなくてはなりません。
利益というものを勘案しない公務員のような仕事でも、「仕事の成果」というのは必ず求められます。
となった場合、簡単に休んでしまったり、辞めたりしてしまう人は採用しないでしょう。
履歴書に高校中退の旨を書けば、中退の理由はかなりの確率で尋ねられると思います。
そこはしっかりと押さえておいてほしいのです。
ただ、中退したからと言って、人生が終わったわけでもないし、そこからいくらでもやり直せる道はあります。
実際、わたしの知っている人で、高校中退後、大検資格を取って、大学に入学し、立派な社会人として働いている人を何人か知っています。
(次回に続きます)
中学生ならびに中学生をお持ちのご父兄様へ 〜高校中退をしないために〜 その4 2016/12/17
(前回の続きです)
現在、高校入試は「多面性を評価する」ということになっています。
事実、面接と作文だけというような推薦入試を行っている私立高校もあります。
特にスポーツ推薦という人であれば、だいたいお勉強の試験は免除されています。
それはそれで、「入学のお手軽さ」にはつながっています。
入学先が決まれば、本人も家族も万々歳です。
しかしそうした場合、推薦入試で通ってきた人は、一般入試を受けてきた人よりどうしても学習面での到達度が低くなりがちです。
となれば、高校中退のリスクは、しっかり勉強をして入学してきた生徒さんに比べて、高くなります。
なぜなら、上述のような中退理由から明らかなように、「高校は勉強をしに行くところ」だからです。
わたしは受験関係者として、生徒さんが希望の高校に合格すれば、それで仕事は達成します。
わたしはそれでいいのですが、中学生の皆さんは、入学が決まった瞬間から、高校における勉強に直面することになります。
ですから、今やっている勉強は、単に入試突破のためだけでなく、「その後」にも大いに関係してくるということを理解していただきたいのです。
.....とはいうものの、高校はそんなに怖いところではありません。
今まで、あまり景気のよくない話ばかりをしてきましたが、きちんと普通に努力してもらえば大丈夫です。
この冬の季節、大変だとは思いますが、しっかりと学習を続けて行って下さい。
受験における「素直さ」とは その1 2016/12/18
受験関係者が語る「成績の伸びやすい生徒さん」の一つの要件として、「素直であること」というのがあります。
この「素直である」という言葉について、もしかするとご父兄の方と認識に差があるかもしれません。
そのようなわけで、今回、わたしの考える「素直さ」について、弊コラムで取り上げてみます。
国語辞典を引いて、「素直」という言葉を引くと、次のような解説があります。
〜性質・態度などが、穏やかでひねくれていないさま。従順。
この説明に異論のある方はないでしょう。
ご父兄や学校の先生方、わたしのような受験関係者にとって、「素直」な生徒さんは、「素直でない」生徒さんに比べて、使うエネルギーが少なくて済むのは間違いがありません。
しかし、わたしは通常の意味として用いられる「素直さ」と、受験における「素直さ」というのは、違いがある、というふうに感じています。
受験における「素直さ」というのは、「受験関係者のアドバイスを聞き入れ、それを実行に移す」ことを意味します。
普通に「素直」な生徒さんであれば、受験関係者の話をよく聞いて、それを実行に移すものと期待しがちです。
が、残念なことに必ずしもそうなっていません。
わたしが、生徒さんにこれこれとアドバイスをすると、生徒さんからは大抵「はい、分かりました」と快い返事があります。
ところが、その実、そのとおりになっていない、ということはよくあります。
(次回に続きます)
受験における「素直さ」とは その2 2016/12/19
(前回の続きです)
「そのとおりになっていない」というのは、二通りあります。
一つは、その生徒さんが、わたしのアドバイスをこなすだけの力を持っていないために、「アドバイスの通りにしたくてもできない」という場合です。
もう一つは、「アドバイスの通りにやらず、自分のやり方でやり通す」という場合です。
前者はしかたがないとしても、後者の場合、あまりにもそれが過度になると、指導そのものが成り立たなくなります。
逆に普段は何かと周りの大人を手こずらせるような生徒さんであっても、自分で納得してわたしのアドバイスを取り入れ、実行に移せば、成績は上がります。
具体例として2名の生徒さんのことを書きます。
一人目の生徒さんは、普段は非常に素直でよい生徒さんなのに、わたしのアドバイスを聞き入れようとしなかったという場合です。
この生徒さんは、クラブチームでラグビーをやっていました。
そちらへの関心は非常に高かったのですが、学習への関心は希薄でした。
「これこれ、このとおりにやって下さい」と指示しても、「はい」というだけで、その通りにしようとしません。
自分がこれまでやってきたやり方を、改めるように指示しているそばから繰り返します。
要するに、わたしの話をさっぱり聴いていないのです。
本人に悪気はないのですが、そうなると結果は出ません。
学習を離れると、ほんとうに素直でよい生徒さんでした。
いくら「素直でよい生徒さん」であっても、成果が出なければ学習指導の意味がありません。
結局その生徒さんは、7か月で指導終了となりました。
「勉強以外で接したかったなあ」というのが、わたしの本音です(笑)
(次回に続きます)
受験における「素直さ」とは その3 2016/12/20
(前回の続きです)
二人目の生徒さんは、一人目の生徒さんとは逆です。
ご父兄からお問い合わせがあったとき、「うちの子は、いろいろと難しくて.....」ということで、初回面談、体験指導をしてみました。
その「難しさ」というのは、何かをするにあたり、いろいろと理屈を言いたがるということでした。
指導を開始すると、確かにご父兄のご心配通りのところはありました。
しかし、よく話を聴くと、「理屈」は言いますが、決して「屁理屈」ではありません。
この手の生徒さんにありがちな、「勉強をしないことを理屈でごまかす」ということはありません。
例えば「自分は数学ならいいのですが、英語の単語は理屈が通ってないんで、覚えられません」というようにです。(実際、このように言っていた生徒さんがいます)
逆にその生徒さんの話を受け止めたうえで、「これこれこうなっているから、そうしてほしい」というようなことを言うと、意外なほど簡単に応じてくれました。
本人には向上心があったので、そうなるとかえって指導は円滑に進みます。
その生徒さんの「理屈のツボ」をしっかり押さえた結果、成績が向上し、仙台向山高校に入学しました。
わたしが言う「受験の上での素直さ」とはこういうことです。
こうしてみると、「受験における素直さ」というのは、本人の性格もさることながら、志気と深く結びついていることが分かります。
わたしとしても、単に家庭教師としての立場を押し付けるのではなく、生徒さんの性格を考えながら、それをなるべく引き出す形で指導を行っていきたいと考えています。
「〇〇は自信ある」と答える生徒さん 2016/12/21
指導をしていると、ときどき「〇〇は自信あります」と言う生徒さんがいます。
例えば、
「連立方程式は自信あります」
「角度を求める問題は自信あります」
というふうにです。
そうしたとき、わたしのほうは、
「ああ、そうですか。では自信があるところで、早速やってみましょうね」
とニッコリほほえみながら答えるのが常です。
しかし、生徒さんには大変申し訳ないのですが、「自信あります」という生徒さんの言葉にはあまり信を置いていません。
そして実際に問題演習をしてもらうと、「〇〇は自信あります」という言葉に反して、いろんな穴がみつかるというのがほとんどです。
このように言ってくる生徒さんのタイプとしては以下の3点が当てはまります。
1.プライドは高いほう
2.それまでいろんな理由で勉強にはあまり積極的に取り組んでこなかった
3.そのため、自分が「理想」とする点が取れていない
だいたいにおいて、よくできる生徒さんの場合、「自信あります」ということはまずありません。
学習をしっかり続けないと、簡単に成績が上がるはずがないということをよく知っているからです。
そして簡単に「自信あります」などと言えるものでもないことも知っています。
自尊心を持って学習を続けていくことは大切ですが、「〇〇は自信あります」という言葉が出てくるうちは、まだまだ学習量が必要です。
ただ、「〇〇は自信あります」といっていた彼らも、ほんとうに成績が上がってくると「〇〇は自信あります」という言葉は出てこなくなります。
まあ、成績ってそういうものなのです。
一高1年生vs二高1年生vs二華1年生 三つ巴バトルの行方 その1 2016/12/22
去る11月に実施された進研模試の実施状況を某所より入手いたしました。
昨年、こちらのコラムで二高1年生と二華1年生の実力分析を取り上げました。
今回はその続編です。
なお、わたしの手元にある資料には、具体的な高校名は記してありません。
しかし受験人数や得点分布が記してあり、そこから学校名を類推いたしました。
ちなみに弊コラムで、昨年7月の段階で、二華1年生の中入組は、最も少なく見積もって半数近くはすでに二高に負けていることが分かると記しました。
このたびの成績を見ると、その差がもっと開いているということが分かります。
そして今回は、一高の1年生とも比較することで、一高、二高、二華の実力がどのような状況になっているのかを示します。
(偏差値80以上の人数)
一高 0 二高 12 二華 10
(偏差値74以上の人数)
一高 10 二高 45 二華 23
(偏差値72以上の人数)
一高 31 二高 72 二華 33
(偏差値66以上の人数)
一高 115 二高 164 二華 72
二華の数字は中入組・高入組を併せたものです。
ただ常識的に考えて、上記の数字はほぼ中入組の数字と言っていいでしょう。
中入組の定員は105名です。
この数字は何を語っているのでしょうか?
(次回に続きます)
一高1年生vs二高1年生vs二華1年生 三つ巴バトルの行方 その2 2016/12/23
(前回の続きです)
昨日示した数字を見ると、(偏差値80以上)という「超トップ層」においては、二高と二華がガップリ四つを組んでいます。
これは十分に予想できます。
二華は今春、東大に8名、二高は7名の合格者を出しました。
二高の東大現役合格者は4名です。
二華のこの数字は中入組の現役の数字でしょう。
この層は、雨が降ろうが、槍が降ろうが、東大のような難関に通ります。
なお、今年の両校の大学合格者は以下の通りでした。
(東大)
一高 1 二高 7 二華 8
(東北大医学部医学科)
一高 2 二高 23 二華 1
(東北大)
一高 79 二高 113 二華 12
このように考えてみると、二高の「超トップ層」は東大でなく、東北大学医学部に進んでいる人たちもかなりいると思われます。
今回、特に印象的なのは、二華中入組の実力です。
昨日の数字によると、「超トップ層」は二高とほぼ互角です。
が、(偏差値74以上)になると、二高がダブルスコアで二華を上回っています。
また(偏差値72以上)の場合、一高と二華はほぼ互角です。
(偏差値66以上)では、一高が二華を完全に引き離しています。
東北大合格者において、一高が二華を圧しているのは、そういった事情も含まれていると思われます。
(次回に続きます)
一高1年生vs二高1年生vs二華1年生 三つ巴バトルの行方 その3 2016/12/24
(前回の続きです)
昨年、弊コラムでは、「二華1年生の中入組は、最も少なく見積もって半数近くはすでに二高に負けている」と記しました。
実際は、「二華1年生の中入組のうち、8割近くは二高のトップ層に及ばず、また7割近くは、一高・二高のトップ層に届いていない」ということだったのです。
二華の中入組の生徒さんたちは、いまさら申すまでもなく、少なくとも小5くらいからは苛烈な受験勉強を行っています。
彼らの勉強の内容というのは、その辺の中3生が裸足で逃げ出すような難しいものばかりです。
一高・二高の入学生は、ほとんどが公立小学校→公立中学校というコースをたどっています。
二華の中入組に比べて、小学生時代の学習量や受験に対する緊張感は比べ物にならないほど少なかったはずです。
また中学入学後、二華の中入組の学習環境は、一高・二高の人たちに比べて、極めてよい状態にあります。
英語・数学のような主要教科の学習量、友人などの学習環境等々、どれをとってもすばらしいものです。
まあ、二華中の場合は、試験で入学者を選抜していますから、公立中学とは全く違った形で受験指導をすることが可能です。
公立中学よりはかなり進度が速く、公立高校入試の範囲に縛られずに授業ができます。
ご父兄も、本人もそれを期待しています。
しかし中学校3年間を経て、同じ土俵に立ったとき、出ている結果は上の通りです。
(次回に続きます)
一高1年生vs二高1年生vs二華1年生 三つ巴バトルの行方 その4 2016/12/25
(前回の続きです)
また一部「受験に造詣の深い」方々の見解によれば、宮城県の「公立小中学校→高校」という高校受験にまつわる環境は次のようなものだとされています。
.....宮城県公立高校入試の内申システムは、実技教科が2倍の換算になったり、ラストスパートを認めないなど鬼畜のようなもの
.....公立中学校というのは、教師にせよ、生徒にせよ、とにかく「環境が悪い」
.....高校受験という「大学受験には無駄な」勉強をしなくてはならない
私立や二華のような中高一貫校と比べると、そういう評価になるのかもしれません。
そのような側面があることは、わたしも十分に理解しています。
しかし、そんなに「劣悪な環境」の下で、「無駄だらけ」の勉強をしてきた一高・二高の人たちが、上記のような結果を出せているというのは、どうしても説明がつきません。
しかも高校入学後、わずか半年を過ぎただけでです。
「無駄だらけ」の高校入試のための勉強も、これを「ホントに無駄」と言えるのは、二華でも1割に満たない人たちだけでしょう。
早い話が、一部の「受験に造詣の深い方々」が金切り声を挙げて非難するほど、内申システムは弊害だらけではないし、高校受験のための学習は無駄ではないし、公立中学は「劣悪な環境」ではない、ということを申し上げたいのです。
それは何よりも結果が物語ります。
宮城県のトップ層の人たちは、お互いの強みを生かして、切磋琢磨していくようにしていけるといいと考えています。
英検取得は高校入試に有利か その1 2016/12/26
先日、中2の生徒さんと次のような会話がありました。
生徒さん: ちょっと聞きたいことがあるんですが、いいですか?
菊池: はい、何でしょうか?
生徒さん: あの、英検って入試に有利なんですか?
菊池: 「入試に有利」.....
まあ、公立高校の前期の出願条件を見ると、英検の3級を取っていれば、評定がよくなくても、出願条件が緩和されるっていう高校はありますね。
ただこれは、出願条件が緩和されるっていうだけで、入試それ自体に点数がプラスされるとか、そういうことはありませんね。
例えば合格点が300点という高校があったとして、英検を取っていたら、280点で受かるとか、そういうことはありませんね。
それから、私立高校だと、推薦入試を行うときに、出願条件が緩和されるとか、そういうことはありましたね。
加点されるところは、あったようななかったような.....
生徒さん: え? そうなんですか?
菊池: ええ、そうですよ。
生徒さん: でも、英語の先生が、英検を取ってると、入試に有利だって言ってたんですよ。
菊池: はあ〜、そうなんですか?
生徒さん: はい、そうなんです。
例えば、一高とか二高とか、英語科のあるところに行くのであれば、準2級を取ってると有利になるって言ってたし、3級を取ってると、有利になるところもあるって.....
(次回に続きます)
英検取得は高校入試に有利か その2 2016/12/27
(前回の続きです)
菊池: 何をもって「有利」っていうかは、いろんな解釈があるでしょうね。
ちなみに一高とか二高に行くのであれば、準2級を取っても、入試の点数がプラスになるとかそういうことはありませんよ。
内申書に書かれることはあるかもしれませんが、「ふ〜ん、そうなんですか.....」ということだけです。
生徒さん: え〜、そうなんですか?
じゃあ、英検、取っても意味なくないですか?
菊池: いや、意味はあると思いますよ。
準2級っていうのは、高校1年生〜2年生にかけてくらいのレベルの英語っていうことです。
ということは、これを取っていれば、高校の授業にはスムーズに入っていけますよね。
そういう意味での有利さっていうのはありますよ。
英語の先生はそう言う意味で、「有利」とおっしゃったのではないでしょうかね?
直接聞いていないので、何とも言えませんが.....
それから大学入試でもAO入試なんかだと、有利な点はありますよ。.....
と、ざっとこんな感じです。
そこで、改めて検索してみると、こういうサイトがありました。
宮城県の高校に関する英検の取り扱いはこうなっています。
英検の取得に「判定優遇」をうたっているのは、育英の推薦入試と西山高校です。
また出願条件の緩和や、高校入学後の単位認定の際に、これが用いられることがあります。
何にせよ、英語を学習するという点で、英検がそのきっかけになれば、損になることはありません。
ただ準2級に合格しても、高校入試で「すごい高得点」を取れるとは限りません。
入試にはそのための対策が必要です。念のために申しておきます。
今日から「お正月前10時間学習会」です! 2016/12/28
今日から2日間、「限定5名まで! お正月前10時間学習会」を開催いたします。
あの暑かった夏休みに「学習会」を開催してから、4か月もたつんだなあ〜と思うと、時間のたつのがいかに速いかを感じます。
今回の参加人員の内訳は以下の通りです。
(28日)
高3 1名 高1 1名 中2 1名 中1 1名 小5 1名
(29日)
高1 1名 中2 1名 中1 2名 小5 1名
中3の生徒さんの参加がないのは、この時期でもほとんどの生徒さんが塾の冬期講習に行っているからです。
この時期ですと、冬期講習も休みになるところが出てくるのですが、中3の生徒さんは塾で頑張っています。
前回の学習会の際も書きましたが、「学習会」のこだわりを書きますと.....
1.参加人数を絞る
この手の講習というと、集めるだけ集め、詰め込むだけ詰め込むというところが多いようです。
わたしはあえて、参加人数を絞りました。
生徒さんの人数を増やせば、わたしだけではとても手が回りません。
そうなると、わたしとは別な方の力を借りなくてはなりません。
それにはちょっと抵抗があったため、今回も「人数限定」としました。
そのため、締め切り後、せっかく申し込みのあった方3名を、泣きの涙でお断りしなくてはなりませんでした。
春休みにもまた学習会を開く計画を立てておりましたので、その際によろしくお願いします。
2.年長者・年少者がともに交われる機会を持つ
上掲の通り、参加する生徒さんの年齢はいろいろです。
もちろん、お互いに顔を知りません。
そうした中で、食事の時間や休憩の時間など、「うちの高校はこんな感じなんだよ」というような情報を発信・受信できる場を設けたいと考えています。
こういう生の情報は非常に貴重です。
単に学習をするという場にとどまらず、「学習の志気を高める」上で、よい刺激になるように、わたしのほうからも水を向けるようにします。
さて、今から学習会に行ってまいります。
進捗状況は、わたしのツイッターにても発信いたします。
「限定5名まで! お正月前10時間学習会」第1日目終了 2016/12/29
昨日、「お正月前10時間学習会」の第1日目が終了しました。
今回はわたしにとって、2回目の学習会となります。
前回の時の経験を踏まえ、よりよい学習会になったのではないかと感じています。
お互いの挨拶もそこそこに早速学習開始です!

学校の課題をする人、通信教育の教材をやる人、通塾中の課題をやる人、様々です。
家庭教師の指導のように、1対1ではないので、わたしの目の届く範囲で、できうる限り平等に指導したつもりです。
まさしく寺子屋!
休憩時間には、「わたしからの差し入れ」ということで、プリンを食べました。

勉強というのは、エネルギーを非常に使います。
そのようなわけで、プリンのような甘いものは、脳へのプレゼントにもなります。
そうこうしているうちに、お昼時です。

これは家内が作ってくれたお弁当です。
昼食後の昼休みには、縁があって集まった生徒さんたちの親睦を図るため、カードゲームのUNO大会をやりました。これが結構盛り上がります。

3回やって、最優秀成績者には、豪華賞品(!)をプレゼントしました。
ちなみに今日のUNO大会優勝者は、高3の生徒さんでした。
午後の部へ入ります。
そして、無事終了となりました。
5時間の学習を終えた生徒さんの顔は、充実した表情が伺えました。
今日もやります!
「限定5名まで! お正月前10時間学習会」第2日目終了!&今年1年ありがとうございました 2016/12/30
昨日、「10時間学習会」、第2日目が無事に終了しました。
メンバーが1人入れ替わり、5人でスタートです。
早速、学習会、スタート!
昨日同様、生徒さんたちはきびきびと学習に向かいます。
バリバリと問題をこなしていきます。
生徒さんの指導をしている様子です。

そしてあっという間に、昼食の時間に。
昼食時間の後には、大好評だった(!?)UNO大会です。
今日の賞品は、これ。

都合3回ゲームを行い、中1の生徒さんが見事に優勝!
賞品を獲得しました。
そして午後の勉強にも身が入ります。
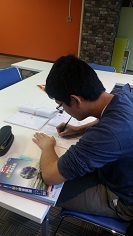
.....
「ちょうど時間となりました」。
生徒さんにも、快い疲れと達成感があったようでした。
すべての日程を終え、ホッとしているわたし。

昨日も生徒さんから聞かれた感想として、
「勉強がはかどりました」
「思っていたよりあっという間に時間が過ぎました」
という声がありました。
わたしの開催した「学習会」は、人数を限定し、わたしの指導が満遍なく行きわたることができ、なおかつ、生徒さん同士の交流、ということを「売り」にしました。
わたしとしては、このようにしてみて、よかったと思っています。
開催するほうからすると、「学習会」は、単に「教える」ことだけが仕事になるのではありません。
会場の手配、入出金に関する業務、会場の空調設備や生徒さんへの目配り等々、いろいろな付帯業務があります。
人数が多くなると、付帯業務が多くなり、そのための人員が必要になってきます。
付帯業務を小さく抑えることで、生徒さんへの指導の時間を確保したいと考えました。
ご父兄の方からは、「また機会があれば、ぜひ参加させたい」とのお声をいただき、次に向けて構想をしているところです。
わたしの年内の業務は、本日1件の指導で終了です。
あとは、事務の仕事をテキパキとこなします!
今年1年、多くの方にご愛顧いただき、深く感謝申し上げます。
そしてつつがなく仕事ができたのは、家族の支えがあったからこそですので、家族にも感謝します。
本コラムの年内中の配信は今日までとし、来年1月3日から再開いたします。
皆様、どうぞよいお年をお過ごしください!
ご利用案内 リンク
お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ
<電話での受付>
15:00~20:00
※日曜日は除く
※電話は
「雅興産(みやびこうさん)」と出ます
成績upのヒント!
教育コラム「雨か嵐か」
プロ家庭教師菊池
住所
〒981-0933
仙台市青葉区柏木1-2-29-301
電話受付時間
15:00~20:00
定休日
日曜日

