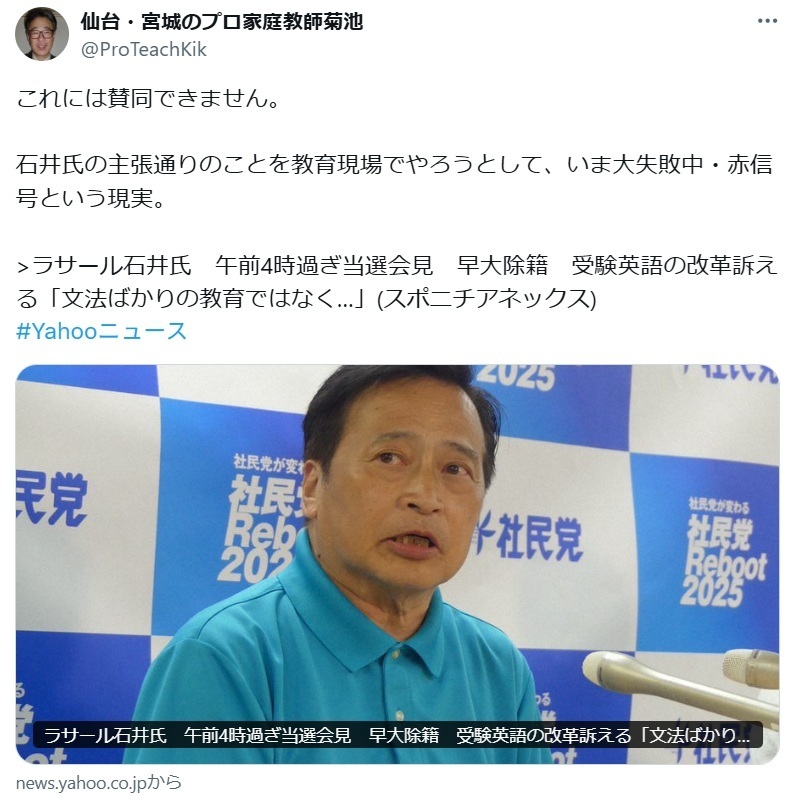〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301
電話での受付:15:00~20:00
定休日:日曜日
ご父兄の皆様 学生時代の学習状況はいかがでしたでしょう? その1 2025/07/01
こちらのコラムは、主としてご父兄向けに、受験や学習に関する話を提供しています。
それゆえここで話題にしているのは、ご父兄から見ると、「息子・娘の受験」「息子・娘の学習」です。
そういう前提があって、皆様にお聞きします。
・・・ご父兄の皆様 学生時代の学習状況はいかがでしたでしょう?
このように言われると、ドキッとするかもしれません。
わたしが同じようなことを聞かれたら、きっとドキッとします。
わたしがなぜこんなことを言ったか...
それは、わたしが指導をして、ご父兄に接していると、次のように感じることが多いからです。
・・・高学歴の方、学生時代に受験学習をガッチリなさった経験のある方ほど、受験に関して話が早い
・・・高学歴の方、学生時代に受験学習をガッチリなさった経験のある方ほど、「子供はまず勉学第一」というお考えである
本コラムをお読みの方は、ほとんどが意識の高いご父兄です。
そういう方から見れば、
「受験に関して話が早い」
「子供はまず勉学第一というお考え」
という「ごく当然のこと」を、なぜ菊池はわざわざ書くのか、という風にお感じになったかもしれません。
しかし、実際にご父兄に接していると、例えば「子供ははまず勉学第一」ということが、必ずしも「当然のこと」ではないと感じるのです。
(次回に続きます)
ご父兄の皆様 学生時代の学習状況はいかがでしたでしょう? その2 2025/07/02
(前回の続きです)
実際にご父兄に接していると、「子供はまず勉学第一」とお考えの方ばかりではない
これはどういうことなのでしょうか。
例えば、以下は、わたしが経験した事例です。
(1)定期試験の1週間前に「家族旅行」と称して、学校の授業・家庭教師の指導を休む
(2)お母様の知人の○○さんが急遽訪ねてくることになって、その関係で家では授業ができないので、指導のキャンセルを当日に申し出てくる
もちろん、「子供の学習」に、どのような価値基準を置くかは、それぞれご家庭によって違います。
ただ、以上挙げた例で指導を休むご家庭というのは、トップ層・上位層の生徒さんのご家庭にはまずありません。
この事例は、公立中学で定期試験5教科150~200点(1科目30点台)の生徒さんのご家庭です。
こちらとしては、生徒さんの成績改善のため、ご家庭に伺って学習指導をしているわけです。
もちろん、ご家庭としてもそれを望んでいるわけです。
しかし、指導の側としては、
「ご家庭でいろんな都合はあるかもしれないが、まずは子息の勉学を最優先する」
としていただかなくては、「成績を上げていく」以前のお話と考えてしまいます。
たぶん、当コラムをお読みのご父兄の多くの方も、わたしと同じようにお考えなのではないでしょうか。
(次回に続きます)
ご父兄の皆様 学生時代の学習状況はいかがでしたでしょう? その3 2025/07/03
(前回の続きです)
前回紹介した(1)(2)の事例について補足です。
この二つのケースは、(2)が「成績がなかなか改善しない」ということで、中2の半ばでご家庭のほうから「指導終了の申し出」がありました。
(1)のケースは、中2の11月末で、こちらから「指導終了」をご家庭に願い出ました。
こちらから「指導終了」を願い出るというのは、受験業界の常識に照らせば、レアケースです。
ただ
「あのとき、契約を続けていたほうがよかったなあ」
と、感じたことはありません。
ということは、そのときのわたしの判断は、妥当なものだったのでしょう。
なお、(1)そして(2)のご家庭の名誉のために申し上げておくと、どちらのご父兄も、問題のあるような方ではありませんでした。
ただ、必ずしも「子供はまず勉学第一」というお考えのご家庭ではなかったということです。
そうなると、成績を上げていくのは、難しくなります。
このように書くと、
「親と子は別の人格だ」
「親が勉学第一と考えなくても、それと子供の成績は関係ないのでは?」
このようにお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、わたしの経験によれば、親御さんの意識と子供の成績とは、大いに関連があります。
(次回に続きます)
ご父兄の皆様 学生時代の学習状況はいかがでしたでしょう? その4 2025/07/04
(前回の続きです)
子供は親のことをよく見ています。
そして、
「うちの子供はなかなか親の言うことを聞かない」
と思っているケースでも、受験指導をしてみると、彼らがいかに自身の親御さんの影響を受けているかが分かります。
これをご父兄ご自身に置き換えてみると、
例えば
・・・自分は勉強が得意ではない
・・・親のほうも特に勉強をやるようにいうタイプでもない
そういう環境にいたら、ご自身は「勉強をやっていこう!」と考えるでしょうか?
積極的に勉強をしていこうという考えには至るのは、なかなかに難しいでしょう。
何しろ、「勉強しないこと」が「親公認」なわけですから。
トップクラスの生徒さんというのは、その生徒さんが優秀であることはもちろんです。
それに加えて、ご家庭が「子供はまず勉学第一」という方針です。
逆にいうと、ご家庭がそういう方針でもない限り、受験の競争は乗り切っていけません。
・・・うちの子供は、そこまで優秀ではないし、親としても高望みはしない
仮にそうであっても、「子供はまず勉学第一」という方針があるかないかでは、子供に与える影響がまるで違います。
そして、それは受験機関における受験指導のときにも、その影響は大いに出てきます。
名取北高と石巻西高 ~東北大合格という「快挙」~ その1 2025/07/05
過日、今春の大学合格実績につき、次のような動画をアップしました。
2025 宮城県高校別 大学進学実績(確定値)
この動画の内容は、県内の高校における東大・京大・東北大の合格実績をまとめたものです。
詳しくは動画をご視聴ください。
さて、わたしがこの種の動画を何度か作っていて、いちばんワクワクするのが、「東北大合格者1名」の高校を確認しているときです。
なぜなら、「意外な高校」がポッと出ることがあるからです。
今年の「東北大合格者1名」は次の通りでした。
ドミニコ、石巻西、佐沼、名取北
ここで、わたしが注目、というよりも驚いたのは、「石巻西」「名取北」という校名です。
正直に告白してしまうと、この2校の字を見たとき、思わず
「え? 石巻西? 名取北?」
と、素っ頓狂な声を出してしまいました。
両校の関係者の方には大変失礼に聞こえるかもしれませんが、それほどまでに、わたしにとっては、衝撃的でした。
県内の「受験の常識」からすると、この2校から東北大合格者が出るということは、かなり考えづらいからです。
そして、両校のサイトで、それが事実であることを確認しました。
合格した方には畏敬の念のようなものを感じました。
(次回に続きます)
名取北高と石巻西高 ~東北大合格という「快挙」~ その2 2025/07/06
(前回の続きです)
前回のコラムで紹介した名取北のみやぎ模試偏差値は2026年版で次のようになっています。
名取北 45
名取北の「偏差値45」というのは、宮城県の高校受験生全体から見て100人中70位くらいです。
西高や東高の英語科とレベル的にはだいたい同じになります。
名取北は毎年、山形大や福島大に2~3名程度の合格者・進学者はいます。
山形大や福島大へは、ナンバースクールからも進学します。
そういうことを考えると、名取北から国公立へ合格するというのも、かなりハードではあります。
そして、名取北の場合、専門学校への進学者+就職者が、全体の約3割弱。
私大へ7割くらい進みます。
国公立へ進む生徒さんは、全体の5%くらいです。
その中でも、東北大となると、ハードルはグッと高くなります。
二高でも、約半数の生徒さんは、東北大合格レベルまで達しません。
そうした現状を考えると、名取北という環境で、東北大を受験し、合格する...
こうした方は、かなり強靭なマインドをお持ちの方です。
仮にわたしが名取北に入学し、そこで3年間を過ごしたら...
きっと東北大へは合格できなかっただろうと思います。
というより、東北大を目指そうという発想まで至らなかったでしょう。
(次回に続きます)
名取北高と石巻西高 ~東北大合格という「快挙」~ その3 2025/07/07
(前回の続きです)
さらに、石巻西のみやぎ模試偏差値は2026年版で次のようになっています。
石巻西 42
前回に紹介した名取北より3ポイント低いです。
仙台地区で言えば、塩釜高校・利府高校と同じくらいです。
3ポイント低いということは、受験で言えば「ワンランクの差」となります。
例えば、二高と一高の偏差値差は2です。
一高と三高の場合は3です。
そもそも石巻地区で、東北大へ行けるくらいの生徒さんは、石巻高校に進学します。
事実、石巻高校からは毎年、1桁台の東北大合格者が出ます。
今年は医医に2名です。
石巻高校から東北大合格者が出るのは、驚きません。
しかし、石巻西は、石巻地区内で石巻・好文館に続く3番手です。
例年、石巻西は国公立への進学者が1名程度いるかいないかです。
ほとんどが私大・専門学校へ進みます。
今年は国公立への進学者が10名いました。
かなりの躍進です。
そしてその中でも、東北大への合格者というのは、光ります。
まわりがほぼ私大・専門学校へ進学するという環境で、東北大に合格できる精神力は、「すごい」の一言です。
ほかにわたしの気持ちを形容する単語が出てきてもよさそうです...
が、どうも見つかりません。
(次回に続きます)
名取北高と石巻西高 ~東北大合格という「快挙」~ その4 2025/07/08
(前回の続きです)
前回までに紹介した名取北・石巻西からの東北大合格者というのは、特にナンバースクールの皆さんに知ってほしいのです。
ナンバースクールの生徒さんたちは、自校の進学実績の大雑把な数字を分かってはいるようです。
自校から東大が何名出ているとか、東北大の合格者がどれくらいかということです。、
ですから、東北大に行くのであれば、校内の順位でだいたいこれくらいは取っておく必要がある、というようなことは何となく知っています。
ただ、他校の数字はどうなっているのかについては、ほぼ知りません。
当然と言えば当然です。
そして、向山や南高、館山あたりからも毎年、多くないとはいえ、合格者が出ていることは、ほぼ知りません。
こうしたことを彼らに示すと、
「エ~?」
というような反応を示します。
声には出しませんが、顔の表情がそうです。
加えて、名取北・石巻西の東北大合格者、みやぎ模試偏差値を示すと、
「....」
と、絶句といった感じで少々うつむき加減になります。
その心情・リアクションは、わたしも理解できます。
わたしも彼らと同じ立場にいたら、そういうリアクションをしたでしょうから。
(次回に続きます)
名取北高と石巻西高 ~東北大合格という「快挙」~ その5 2025/07/09
(前回の続きです)
向山や南高、あるいは名取北・石巻西から東北大に合格した生徒さんからすれば、ナンバースクールの生徒さんというのは、「受験の王道を歩いてきた」と見えるはずです。
「受験の王道を歩いてきた」...
これが言い過ぎであれば、「自分たちより受験に適した環境の下で3年間を過ごしてきた」と考えているはずです。
この点、ナンバースクールの生徒さん自身は、あまりそういうことを意識していないでしょうけれど。
名取北・石巻西であれば、クラスメイトのかなりの人が、専門学校へ進学したり、就職したり、私大へ行きます。
そうした環境の中で、適切な受験情報を得て、東北大に合格できるだけの学力を積み重ねていくというのは、並大抵のことではありません。
少なくともわたしにはできそうにありません。
・二高においても、半分の生徒さんは東北大に合格できるところまで達しないという「現実」
・一高においても、3分の2の生徒さんは東北大に合格できるところまで達しないという「現実」
・一方で、偏差値40台の高校からも東北大に合格できるところまで達している生徒さんが出ている「現実」
これらの点、特にナンバースクールの生徒さんは、心にとめておいていただきたい「現実」です。
気づきづらい「国語の単語力」 その1 2025/07/10
多くの方は受験で「単語」という言葉を聞くと、頭に浮かぶのは「英単語」のことではないでしょうか。
事実、英語では「英単語を覚える」ことが最重要課題です。
「英単語の記憶」は、英語の上級者になっても続きます。
一方、「単語の記憶」ということについては、「英単語の記憶」以上に大切なものがあります。
「国語の単語力」です。
この「国語の単語力」というのは、例えば公立高校の入試であれば、次のような単語をきちんと知っているかがカギです。
・~であることを余儀なくされる
・感銘を受ける
・生気のない顔
共通テストレベルの大学入試問題は次のような単語について、知っているかどうかです。
・罪をあがなう
・あれこれ詮索する
・ポストモダン
これらの単語・言い回しは、日常生活の中でそう頻繁に出会えるものではありません。
そして、こうした単語を知っているか、意味はきちんと分かるか、というのは、気づきにくいです。
学習が苦手層に近づくほど、このような単語・言い回しの意味するところの理解度が浅いです。
「どこかでは聞いたことがあるような気がするが、意味はよく分からない」...
こういうものが多くなればそれだけ、文章の読解力は落ちます。
それが国語のみならず、全教科に影響を与えます。
(次回に続きます)
気づきづらい「国語の単語力」 その2 2025/07/11
(前回の続きです)
「国語のテストの点がよくない」
このように言ってくる、あるいはそう感じている生徒さんは、意外といます。
そのような生徒さんは、だいたい次のような特徴があります。
・全体の上位3分の1くらいに所属している
・他の科目に比べて国語の成績に落ち込みがある
ここで上位3分の1未満の生徒さんは、「国語の単語力」という点で、もちろん足りていません。
ただ、そういう生徒さんは、「国語の単語力不足」について、自覚するのは難しいのです。
周囲の方々も、彼らの「国語の単語力不足」には気づきにくいです。
というのも、国語以外の科目での不足が、「国語の単語力不足」以上に目立ってしまっているからです。
では、具体的に「国語の単語力不足」とはどういうことか。
以下、例を出します。
「A君は、クラスメイトの前で、自分の過失認定を余儀なくされた」
→生徒さんへ「これってどういう意味ですか?」と質問
→生徒さんからは、
「A君は自分が間違ったと認めなかった、みたいな感じかなあ?」との回答
こういうケースが、意外と多いのです。
そういうことが重なれば、国語の読解問題は正解にたどり着くのが難しくなってしまいます。
(次回に続きます)
気づきづらい「国語の単語力」 その3 2025/07/12
(前回の続きです)
それから「文章読解力」に関しては、こういうことがありました。
以前に、中学生以上の生徒さんに、次のような文章読解力テストをしたことがあります。
<問題>
ここにA,B,C,Dという4人の人物がいます。
Aの父方の祖父母と、Dの母方の祖父母は同一人物ですが、Aの母方の祖父母と、Dの
父方の祖父母はそうではありません。
またAの父であるCは40歳、Dの母であるBは38歳です。
問 ( )に当てはまる親族名称を答えなさい。
(1)DはAの( )です。
(2)CはBの( )です。
これの答えは
(1)いとこ
(2)兄
この問題は、学習苦手層の生徒さんの場合、家系図がほぼ書けません。
家系図が書けないと、この問題は解けません。
また問題文には、難しい単語がほぼないにもありません。
しかし、「いとこ」というのは、「親同士が兄弟姉妹である」という知識も、学習苦手層になると「常識」ではないようです。
この辺りは「常識的なことを知っているか、知らないかというところに帰着します。
こうした「基本的・常識的なことをわきまえているか」も、「国語の単語力」と大いに関係があります。
「凡ミス」という言葉 大嫌いです! その1 2025/07/13
わたしの嫌いな単語に「凡ミス」というのがあります。
より正確に言えば、生徒さんが「凡ミスだった」と発言したときの表情などに、非常に苛立ちを覚えます。
「凡ミス」という単語を聞くのは、だいたい次のようなケースです。
・平均点に達しない男子生徒から発せられることが多い
・「凡ミス」は、これまでに何回・何十回と間違ってきている事項
・「分かってたんだけど『凡ミス』して間違った」という趣旨の発言をする
・「凡ミス」を直そうという姿勢がほとんど感じられない
・このワードを使う生徒さんは、高い確率で私立高校推薦で進学
要するに、あまり学習への関心が高くないという生徒さんから、「凡ミス」という言葉を聞くことが多いのです。
わたしとしては、生徒さんの「凡ミス」そのもの以上に、「凡ミス」をなくそうとしない姿勢に、大いなる怒りを感じてしまいます。
「凡ミス・凡ミスって、そんなに大したことのないものなら、なぜに何度も間違う?」という怒りです。
若いころには、この「凡ミス」のことで、幾度となく「喝入れ」をしたりしたものでした。
最近は、「喝入れ」の頻度も落ちています。
年齢のせいでエネルギーが減ってきたのか、あるいは達観してしまったのか...
(次回に続きます)
「凡ミス」という言葉 大嫌いです! その2 2025/07/14
(前回の続きです)
「凡ミス」をなくそうという姿勢のないのは、「それなりにできる」生徒さんにもいます。
「それなりにできる」というのは、公立中学の生徒の中で、上位3分の1以上、みやぎ模試偏差値55以上程度を意味します。
彼らがもともと持っている素質は、決して他と比べて劣っているわけではないのです。
ただ、頑固さというか、おかしなプライドみたいなのは、人一倍強いという印象です。
それゆえに、受験指導者のアドバイスを受け付けないというケースはあります。
そういう生徒さんは、当然ながら、当初の志望に合格することはありません。
だいたいそういうタイプの生徒さんは、自身の成績よりかなり高めなところを入試では受けるからです。
ハイレベルな集団の中で、彼らは淘汰されてしまいます。
当然ですが。
彼らの持っているものは悪くはないのです。
残念な話ではあります。
逆に、平均まで達しないという生徒さんでも、「凡ミス」をなくそうと努力する生徒さんはいます。
だいたい、そういう生徒さんは「凡ミス」という言葉を使いません。
彼らは、素直に、そして愚直に受験指導者のアドバイスを受け入れようとします。
(次回に続きます)
「凡ミス」という言葉 大嫌いです! その3 2025/07/15
(前回の続きです)
前回のコラムでは、平均まで達しないという生徒さんでも、「凡ミス」をなくそうと努力する生徒さんはいるとお伝えしました。
そこから話を続けます。
そういう生徒さんは、確かに多いわけではありません。
「凡ミス」をなくそうという意識があまりないからこその「平均突破できず」ともいえます。
しかし、だからこそ、もともと「持っているもの」は少ないとしても、「凡ミス」をなくそうと努力する生徒さんは貴重です。
彼らは、当然ながら、入試ではトップクラスと戦うわけではありません。
競争相手の意識は必ずしも高くありません。
そのため、彼らは第一志望に合格していきます。
逆にいうと、「平均まで達しない」という生徒さんの層であれば、わずかでも「凡ミス」をなくそうと思って学習に臨む生徒さんは強いです。
かく言うわたしも、現役生徒の頃は、もちろん試験でミスをしていました。
ただ、ミスがあったら、悔しがって、
「なんでこんなミスをしちゃったのか?」
「次にこんなミス、しないようにするにはどうしたらいいのか?」
ということは、いつも考えていました。
各種の試験を見ていて思うのは、「ミスをしないこと」の大切さです。
「ミス」をゼロにするのは、難しいです。
が、より少なくすることはできます。
わたしが申しあげたいのは、この点につきます。
続編 勉強のやり方だけを教わっても… その1 2025/07/16
先般、「勉強のやり方」に関して、次のようなコラムを書きました。
<関連コラム>
今回は、この続編です。
前回、ちょっと言い足りないことがあったものですから...
わたしがこの「続編」で主にお伝えしたいのは、
「勉強のやり方」を教えられても、それだけで成績は改善していかない
という点です。
言い換えると、教えられた勉強のやり方を自分で実際にやることなしに、成績が上向いていくことはないということです。
「当たり前でしょ?」
「何を言ってる?」
そのようにお感じになった方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、これが「当たり前」ではないのです。
成績が平均よりずっと下という生徒さんのご父兄に、この点をご理解いただけない方が意外といらっしゃるのです。
「勉強のやり方を教えてもらえば成績は上向いていく」
→「だから勉強のやり方・コツのようなものを教えてもらうだけでいい」
→「それを教えてもらえば、あとは子供が実践できる」
→「ホンネを言えば、できる限り塾関連の費用は抑えておきたい」
というお考えのようです。
(次回に続きます)
続編 勉強のやり方だけを教わっても… その2 2025/07/17
(前回の続きです)
「できる限り塾関連の費用は抑えておきたい」
ご父兄のほうとしては、「安かろう悪かろう」には、相応の理由があることはよくご存じです。
ただ、その一方で
「コストはできるだけかからないほうがいい」
こう考えるのは、人情です。
これは塾関連に限らず、です。
ですから、
「コストはできるだけかからないほうがいい」
→「だから勉強のやり方・コツのようなものを教えてもらうだけでいい」
→「それを教えてもらえば、あとは子供が実践できる」
とお考えになるのは、よく理解できます。
しかし、「勉強のやり方・コツのようなもの」を教えられて、それができて、結果を残す生徒さんは、かなり優秀です。
成績が平均よりずっと下という生徒さんは、「勉強のやり方・コツのようなもの」を教えられて、できることは相当に限定的です。
それでも、小学校でやる単元テスト(受験業界でいう「カラーテスト」)くらいなら、1週間くらいの猛勉強で、磯野カツオ君クラスの生徒さんも、ちょっとくらいは点数が上がります。
が、中学校の中間テスト・期末テストくらいになると、太刀打ちできません。
小学校のときより、学年が進んでいます。
範囲も小学校のカラーテストより広いです。
(次回に続きます)
続編 勉強のやり方だけを教わっても… その3 2025/07/18
(前回の続きです)
前回に引き続いてさらに申し上げます。
特に公立の小中学校で、成績が平均よりずっと下という生徒さんの場合、
「教えたことをきちんとやれる」
などということは、極めて稀です。
指導時間は限られています。
加えて、彼らは
「何とかして覚えてやろう!」
というように、やる気が満ちあふれている生徒さんはかなり少数派です。
さらに、教えても、時間がたてば「抜けていくもの」は、ご父兄が想像する以上に多いです。
「勉強のやり方・コツのようなものを教えてもらうだけでいい」
→「それを教えてもらえば、あとは子供が実践できる」
このようにお考えになっていらっしゃる方は、彼らが「指導をしたそばからどれだけ抜け落ちていくか」ということも十分に、十二分にお考えいただきたいのです。
これは、会社に入ってきた新人君・新人ちゃんの指導係をお務めになったことのある方なら、お分かりいただけるはずです。
新人君・新人ちゃんなら、取りあえずは給料のための仕事としてやっています。
生徒さんは、必ずしも志気が高いわけではありません。
受験指導者から給料をもらえるわけでもありません。
指導内容が定着するまでに、かなりの時間と労力がかかるというのは、そういう背景でとらえていただけると幸いです。
なぜ受験情報は「上位校」にばかり集中する? その1 2025/07/19
以前に当方の動画チャンネルをご覧になったご父兄から、こんな話を聞いたことがあります。
・・・うちの子供は不登校で、私立の推薦入試に出願しましたが、合格できませんでした。
通信制の高校への進学を考えています。
でも通信制高校の情報って、少ないんです。
学校のホームページはあるんですが。
「親から見た情報」がとても少ないです。
できる子供さんが行くところは、たくさんいろんな情報があるんですが・・・
さて、ここでご父兄が仰った「親から見た情報」というのは、学校からの公式情報ではありません。
その学校の評判・口コミとか、公式には現れてこない情報です。
学校からの公式情報には、「学校にとって必要なこと」「学校にとって良いこと」が書いてあるだけです。
そして、通信制高校のようなところだと、「親が欲しい情報」が、手に入れづらいわけです。
逆に、「上位校」となると、評判・口コミのように「親が欲しい情報」を、何らかの形で手に入れることができます。
これはなぜなのか、以下ご説明いたします。
結論を申し上げますと、
「『上位校』には需要があるから」
です。
逆にいうと、通信制高校のようなところは、「上位校」に比べて、需要が少ないということです。
(次回に続きます)
なぜ受験情報は「上位校」にばかり集中する? その2 2025/07/20
(前回の続きです)
「上位校の受験情報には需要がある」
これもう少し掘り下げます。
「上位校の受験情報」という点で、まず思い当たるのが東大の受験情報です。
入試解説、合格者の体験談、その他いろいろな情報が手に入ります。
受験生の中でも、東大に合格できるレベルの生徒さんは、圧倒的に少数です。
しかし、受験情報の中で、最も入手しやすいのは、東大関連です。
これをビジネスで情報発信する側から見ると、どう映るか。
「上位校の受験情報には需要がある」
=「上位校の受験情報はカネになる」
です。
そして、受験情報を趣味的に発信している方、あるいは承認要求を満たしたいという方であれば、
「上位校の受験情報には需要がある」
=「上位校の受験情報はモチベーションになる」
です。
わたしの場合、受験情報の発信は宮城県内の受験生・ご父兄に向けています。
その際、最も反応のあるのは、
「上位校=特に仙台一高・二高関連の情報」
です。
ここでいう「反応」とは、ネットのアクセス数やアクセス時間・コメント数などです。
一高・二高関連のテーマは、例えば偏差値40付近の○○高校・△△高校の情報に比べると、「反応」は何倍も違います。
(次回に続きます)
なぜ受験情報は「上位校」にばかり集中する? その3 2025/07/21
(前回の続きです)
わたしの場合、このコラム・YouTube動画の発信は、自身の広告宣伝のためです。
自分の持っている情報あるいは受験に対する考え方を公にし、ビジネスにつなげるということが目的です。
ですから、できる限り反応が来る発信を心がけています。
となれば、需要の少ないテーマでの発信は避けるようになります。
もっともわたしの場合は、反応の少ないテーマでの発信もまるっきりしないわけではないですが。
あまりに似たようなものばかりになると、ご覧になる方も飽きてくるでしょうから。
ただ、反応が少ないようなテーマは、実のところ、あまりモチベーションが上がりません。
楽屋話を表に出してしまいますが、これはたぶんどなたも同じだと思われます。
「上位校」の場合、ご父兄は情報収集に熱心です。
当然と言えば、当然と言えるでしょう。
もともとそういうご父兄は、教育熱心です。
加えて、子供が「上位校」を目指すとなれば、情報をできる限り集めようというモチベーションも高まります。
「上位校」の受験情報に対する需要というのは、こういう背景もあります。
となれば、「上位校」から下に離れていくほど、受験情報を得るのは難しくなっていきます。
「勉強を教える」のではなく「成績を上げる」とはどういうこと? 2025/07/22
当方は受験指導に当たって、
「勉強を教える」のではなく「成績を上げる」
ということをうたっています。
今回のコラムは、このフレーズの意味を詳しく述べてみます。
普通、学校でも、受験関係者であっても、「教師」と名が付けば、それは「勉強を教える人」です。
もちろん、わたしも「勉強を教える人」ではあるわけです。
しかしわたしは、それだけでは不十分と考えています。
必要なのは、「成績を上げる」ことだと考えるからです。
ですから、
「勉強を教える」のではなく「成績を上げる」
=「勉強を教えただけでは仕事が完結しない」という気持ちで指導に臨む
このようにご理解いただくと幸いです。
ただ、わたしが指導をすれば、たちどころに成績がみるみる上がっていくわけではありません。
わたしがやれることは、「生徒さんのお手伝い」です。
成績が上がっていくためには、こちらとしても、生徒さんにはそれ相応の要求をします。
その要求というのは、
「生徒さんの現状をよく認識して彼らができる範囲のことを最大限に頑張ってもらう」
ということです。
こうした考えのもとに指導に臨んでいること、お分かりいただければと思います。
不登校生のお引き受けについて ~受講を検討されている方へ~ その1 2025/07/23
「プロ家庭教師菊池」は、不登校生あるいは「ほぼ不登校生」「やや不登校生」をお持ちのご家庭からも、指導のご依頼があります。
その性質上、不登校生は家庭教師という指導形態をとらざるを得ないケースがかなり多いのかと思います。
今回のコラムでは、不登校生の指導を受け入れる側が、不登校生の受け入れに対してどう考えているかをお伝えいたします。
◎「継続した定期指導ができるか」を最重要視する
不登校生を指導する場合、わたしが最も重視するポイントは
「継続した定期指導ができるかどうか」
です。
不登校生の中には、心の病気や起立性調節障害などで苦しんでいる生徒さんがいます。
そうした生徒さんの場合、「継続した定期指導ができるか」は、一つのポイントになります。
ただ指導があればいいわけではありません。
「継続した定期指導」である必要があります。
なぜ「継続した定期指導」が大切なのか...
理由の一つとして、そもそも学校の学習内容というのは、継続した学習が必要だからです。
だからこそ、生徒さんは休みの日などを除けば、毎日学校へ行くことになっているわけです。
それは、家庭教師という指導形態をとっても同じです。
(次回に続きます)
不登校生のお引き受けについて ~受講を検討されている方へ~ その2 2025/07/24
(前回の続きです)
◎「継続した定期指導」を重要視するのは「受講システム」も関係している
「継続した定期指導」を最重要視する理由は、前回のコラムで述べたことばかりではありません。
家庭教師という指導形態の「受講システム」も絡んでいます。
家庭教師の場合、基本的には「指導をした」ことに対して料金が発生します。
ですから、「指導をした」事実がなければ、原則として料金は発生しません。
ここが、例えば、進学塾のように1教室に10名・20名といった生徒さんを抱える業態とは違います。
不登校生の場合、特に心の状態が不安定だったりして、突然に「体調不良により指導キャンセル」になるというケースが意外と多いのです。
そうなれば、原則として料金は発生しません。
こうしたことがたびたび重なれば、指導をする側としてもビジネスリスクが大きいと考えるようになります。
こういう点が、学校の先生・集団指導塾とは大きく違います。
そのため、こちらのほうから指導契約の打ち切りをご家庭に申し出たことは、これまでに何度かありました。
生徒さんやご父兄には申し訳ないことではあるのですが、ビジネスとして成立しないことをやり続けていくことは、困難です。
(次回に続きます)
不登校生のお引き受けについて ~受講を検討されている方へ~ その3 2025/07/25
(前回の続きです)
◎「継続した定期指導」を重要視するのは他のご同業者も同様
「継続した定期指導」を重要視するのは、たぶんわたし以外のご同業の方も同じです。
「突然のキャンセル」により、指導の予定が空くというのは、この業界の常です。
業界に携わるほうは慣れっこになっている部分があります。
その「突然のキャンセル」に対して、寛容の度合いも、指導者それぞれです。
ただ、ハッキリしているのは、この「突然のキャンセル」を嬉しがっている講師はいないということです。
さらに「突然のキャンセル」が続いてしまうと、自然消滅的に指導契約終了となることが多いのです。
・・・・今回のコラムでは、特に「体調不良によるキャンセル」について述べてきました。
もちろん、不登校になっている生徒さんでも、指導は休まずに継続しているというケースは、これまでも経験してきています。
こういう生徒さんは、不登校でない生徒さんと全く変わりません。
ただ、不登校となっている生徒さんが指導を受ける場合、「指導する側」がどういったことを考えているのか、を知っておくのはムダになりません。
こうした知識で、後々のトラブルは少なくなると思われます。
「転ばぬ先の杖」ということでご理解ください。
受験制度をいじりたがる政治家の先生方 ~迷惑です~ その1 2025/07/26
過日、Twitterで上記のようなツイートをしました。
わたしのように感じた方は多かったようです。
学校の英語の先生・受験関係者に、わたしと同じ趣旨のツイートをされていた方が多くいらっしゃいました。
ラサール石井議員は、この件に関して、次のように発言しています。
・・・昔から思っていたのは、英語教育の改革。
受験のための文法ばかりの教育ではなく会話を中心とした教育に変換して、高校卒業時に全ての人が聞いて話せる英語教育に変えれば日本の力は上がるんじゃないか
ラサール石井議員は、名前の通り、ラサール高卒業です。
この方がラサールにいたころは、ラサールの黄金期でした。
東大合格者のトップ5の常連です。
彼が高校生まで行われてきた英語教育は、バリバリの受験英語だったはずです。
それゆえに、彼がなぜそういう発言をするのか、理解できなくはありません。
しかし、現状の英語教育は、メチャクチャになってしまいました。
石井議員の言うように、文法を軽視し、会話などに比重を置いた結果です。
「できる子はもっとできるようになった」
「できない生徒さんはさらにできなくなった」
こうした二極分化がさらにひどいことになってしまったのです。
(次回に続きます)
受験制度をいじりたがる政治家の先生方 ~迷惑です~ その2 2025/07/27
(前回の続きです)
わたしを初め、英語の教育に携わっている側は、学校での英語教育がいかにひどいかを毎日見せつけられています。
そういう身として、今の現場を知らない政治家先生が
「受験のための文法ばかりの教育ではなく会話を中心とした教育に変換して...」
などというのを聞くと、文句の一つぐらいは言いたくなります。
「失礼ですが、ラサール石井先生、今の学校現場がどうなってるか、現場の英語の先生からお話を聞いたことはおありですか?」
これまで受験関係者は、偉い政治家の先生方などが、思い込みだけで制度を「改革」する様子を、ずっと見せつけられてきました。
例えば大学入試の共通テストです。
以前は、センター試験が行われていました。
前身だった「共通一次」を含めると、40年近くです。
これを、下村博文さんという代議士さんが、文科大臣の頃
「センター試験をやめて別のテストをやろうぜ」
ということで、「新しい試験」をやることになりました。
しかし、実施直前でシステム変更に問題の多いことが発覚。
「センター試験」のシステムがかなり残ることになりました。
わたしはそのドタバタ劇を見ていて、
「だから言わんこっちゃない...」
と呟いていました。
(次回に続きます)
受験制度をいじりたがる政治家の先生方 ~迷惑です~ その3 2025/07/28
(前回の続きです)
「理想の形」を追い求めて「改革」をした結果、「これじゃあ前のほうがよかった」となるのは、世間によくあることです。
前回のコラムで紹介した「共通テスト」導入のドタバタは、ほんの一例です。
あれはまだ「未遂」の段階で済んだから、傷口は浅かったのです。
「受験のための文法ばかりの教育ではなく会話を中心とした教育に変換して...」
これは「理想の形」ではあります。
わたしも「理想」としては、ラサール石井議員と同じ考えを持っています。
しかし、わたしは現場を知っています。
彼のコメントには賛成できません。
ラサール議員がコメントする以前に、お上が「理想の形」を追い求めています。
結果、文法教育は以前に増してひどいことになってしまっています。
そして英語が分からないという生徒が増えすぎて、追い求めた会話中心の教育もままなりません。
何やらイソップ寓話にでも出てきそうなお話です。
そして、こういう教育システムを推進したお上や政治家先生は、責任を取ってくれるわけではありません。
本欄をお読みのご父兄におかれては、お上や政治家先生の行う「新システム」が、必ずしも良い結果をもたらすものではない点、ご留意いただければと思います。
君たちが二十歳になったら ~「手取り額」から受験勉強を考えてみた~ その1 2025/07/29
過日の指導のとき、わたしは、とある生徒さんへ、以下のように話をしました。
・・・今、君は受験学習に取り組んでるわけですよね。
わたしも、もちろん、生徒の頃はありました。
自分は昭和の真っただ中に生まれて、いまよりは子供の数も多かったです。
ですから、受験競争も今以上に大変でした。
ただ、わたしの世代は、就職に関していうと、いまの生徒さんたちよりずっと楽でしたよ。
「バブル」が崩壊して、就職がものすごく大変になったのは、わたしのときより、ほんの少し後の世代の方たち。
君たちの世代は、少子化で、受験競争については、わたしの世代より緩いところは相当にあります。
最難関のところは、ずっと厳しいままですが。
でも、君たちの世代は、社会に出てからが大変なんですよ。
大変なのは、税金以上に社会保険料です。
年金とか、健康保険料とか。
いま、病院に行って1,000円払ったとしましょう。
あれ、ホントは3,000円くらいかかってるんです。
残りの2,000円は、ご両親のお給料から自動的に引かれちゃってる分から出てるんです。
でも、わたしが就職したころの負担は、同じ治療なら300円で済んでました。
そしてお給料から自動的に引かれる分も、今に比べればずっと少なくて済んでたんです。
君たちの世代、大変でしょ?
(次回に続きます)
君たちが二十歳になったら ~「手取り額」から受験勉強を考えてみた~ その2 2025/07/30
(前回の続きです)
今のシステムって、若い世代がおじいちゃん・おばあちゃん世代の方たちへ「強制的に仕送りしてる」っていう仕組みなんです。
君が社会に出たらもらうお給料から、税金とか社会保険料を差し引いた残りが、君の実際のお給料になります。
これを「手取り額」っていうんですね。
おじいちゃん・おばあちゃんの世代の方も、若いころにはそうだったんですよ。
でも、負担してる金額が君の世代に比べると、ずっと少なくて済んでたんです。
「手取り額」というか「手取りの割合」はおじいちゃん・おばあちゃん世代の方のほうが多かったということです。
おまけにその昔は、銀行に預けると「金利」が、今に比べて、信じられないほど高かったんです。
40年前なら、銀行に100万預けたら、1年後には105万になったりしました。
でも今、そんな商品があったら、詐欺ですよ(笑)
せいぜい2~3000円でしょうね。
わたしは、銀行に100万預けたら、1年後には105万になったりする時代に育てられたんです。
40年前よりは高齢者がずっと増えてて、君の世代は人数が少なくなる一方。
君の世代は、社会に出たら、40年近くずっと高齢者に仕送りをし続けなくちゃならないんです。
(次回に続きます)
君たちが二十歳になったら ~「手取り額」から受験勉強を考えてみた~ その3 2025/07/31
(前回の続きです)
わたしが何を言いたいのか...
「受験勉強は将来のために」
こう君は考えているかもしれないし、そんなことは考えないかもしれません。
でも、いまさっきわたしが言ったようなことを頭に入れながら受験勉強をやるのと、そうでないのとでは、
「受験勉強をやる意味って何?」
っていうのに違う視点が加わっていくってことですよ。
当たり前ですが、受験学習って大変です。
だから、ただ「勉強やれ!」って言われたって、ホイホイとできるもんじゃないんですよ。
だいたい、十代半ばの時期、受験学習の意味なんて分からないです。
社会に出て、働いて、お給料をもらうようになって、初めて分かるものです。
偉そうに、いまこんなことを言ってるわたしだって、中学生のころには受験学習の意味なんて、分からなかったし、考えたこともなかった。
いまやってる受験学習って、そのままの形で使うことは決して多くはありません。
でも、そこで学習したこと、特に義務教育でやっているようなことは、知ってるのと、知らないのとでは、知ってるほうが得をすることは多いと思いますねえ。
・・・さて、生徒さんにはどのくらい通じたでしょう?
生徒さんは、結構神妙な面持ちでした。
やっぱりお金の話に絡めると、リアリティが増すっていうことなのかもしれません。
ご利用案内 リンク
お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ
<電話での受付>
15:00~20:00
※日曜日は除く
※電話は
「雅興産(みやびこうさん)」と出ます
成績upのヒント!
教育コラム「雨か嵐か」
プロ家庭教師菊池
住所
〒981-0933
仙台市青葉区柏木1-2-29-301
電話受付時間
15:00~20:00
定休日
日曜日