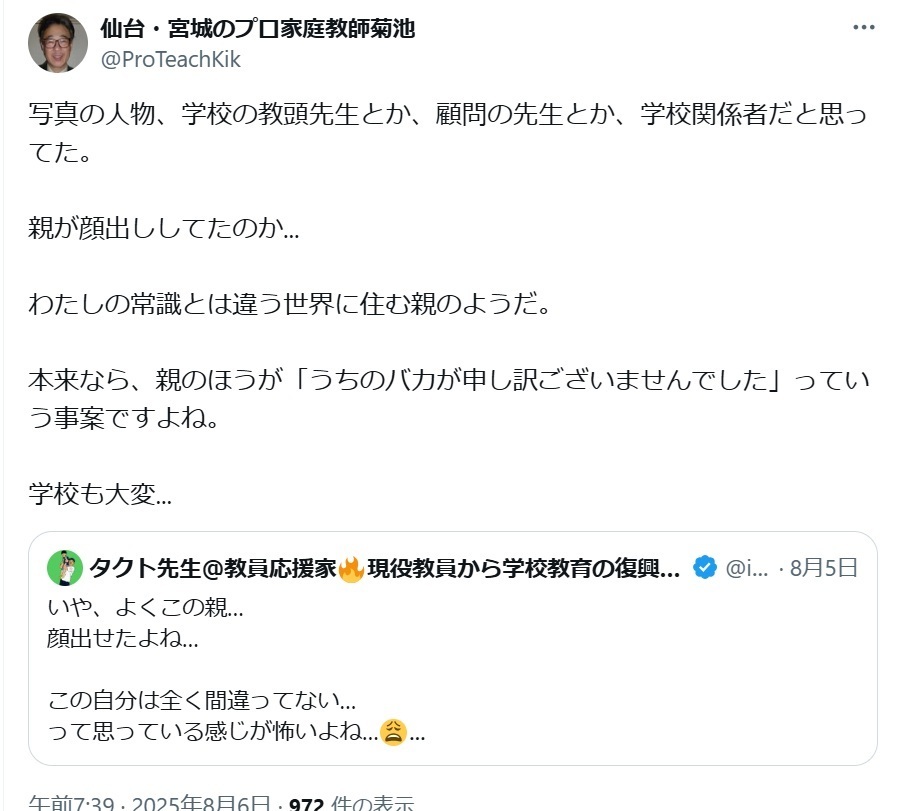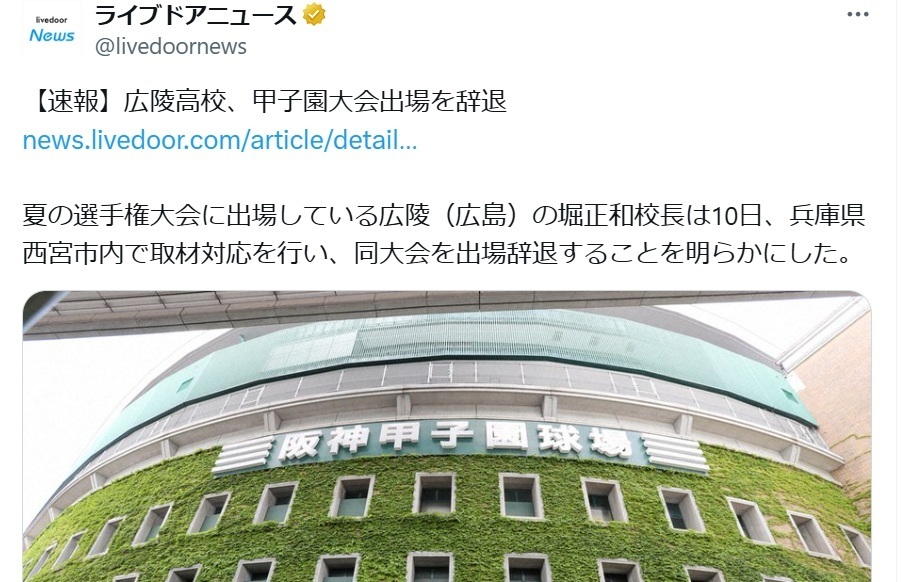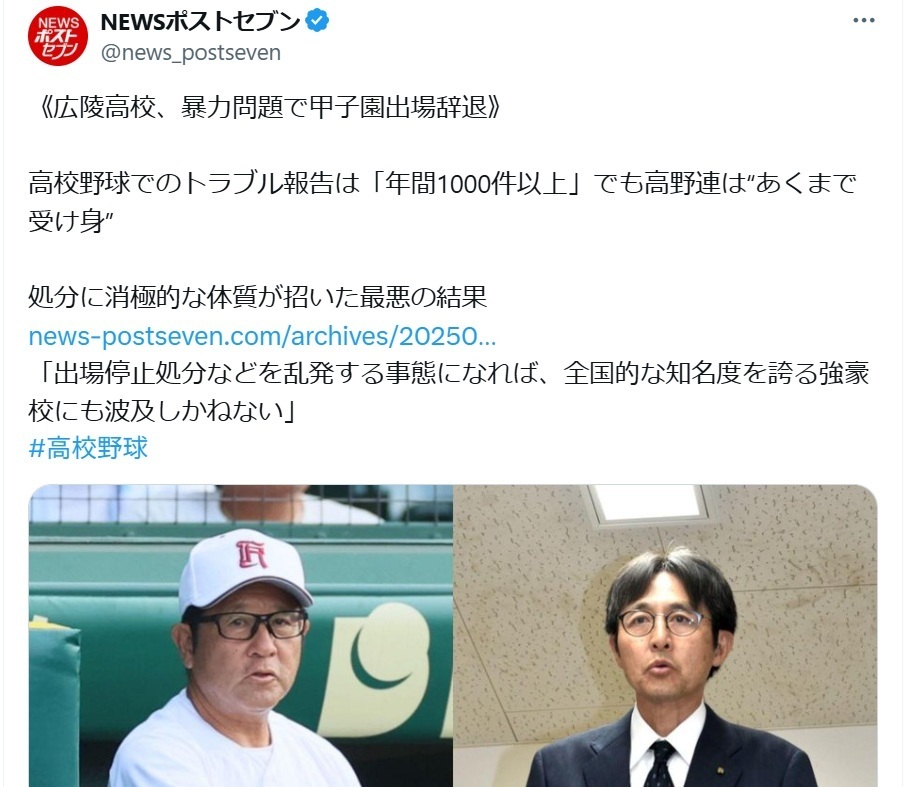〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301
電話での受付:15:00~20:00
定休日:日曜日
今日でコラムは12歳になりました 2025/08/01
今日は8月1日です。
当コラムは、本日で満12歳となりました。
長かったような気もするし、あっという間という気もするし、という感じです。
本欄は、お盆期間・お正月を除いて、ほぼ毎日更新しています。
以前は、こんな感じでやってました。
◎2013年8月1日 コラム連載開始
「1日1コラム」ただし、「週休二日」
→2014年1月から「週休一日」
→2015年2月から「月月火水木金金」
コラムを書き始めたころとの違いは、YouTube動画の存在です。
このYouTube動画は、コラムと相当に勝手が違います。
コラムは文字だけの情報です。
YouTube動画は、映像と音声が主です。
分かりやすさという点で、文字だけの情報はYouTube動画にかないません。
ちょうど、これは「テレビとラジオの関係」と言ってよいかもしれません。
またわたしの場合は、Twitterもあります。
こちらはこちらで、YouTube動画やコラムにはない「機動力」があります。
わたしとしては、動画で発信したことをコラムやTwitterで発信したり、またコラムで扱ったことを動画でリメークしたり、内容を加えたり...
ということを引き続き行ってまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
中高校生の頭痛・腹痛 ~よくなるためには?~ その1 2025/08/02
最近、思い立つことがあって、生徒さんに自分の健康上の問題について、話を聞く機会を持ちました。
彼らの話を聞いてみると、何かしらの健康上の問題を抱えているという生徒さんが意外にいることにちょっと驚きました。
そうした中で、
「これはちょっと困るなあ」
と思ったのが、突発的に起きる頭痛・腹痛です。
生徒さんの中には、慢性というわけではないが、突発的に頭が痛くなったり、腹が痛くなったり、という持病を抱えるケースがありました。
そしてそれは、試験を受けているとき、試験を受ける直前にもあるということです。
こんな風に「爆弾」を抱えたままでは、成績にも支障が出てしまう可能性が出てきます。
こうしたことが起きる原因は、様々でしょう。
体のほうに大きな病気が隠れているとか、そういった場合も考えられます。
そのときには、なるべく早くに医療機関の受診を勧めたいと思います。
ただ、困ってしまうのが、医療機関に行っても、その原因がハッキリしない場合です。
医療機関に行くと、レントゲンやMRIを撮って、そこで異常が見つからないという場合もあります。
そういった場合だと、痛みの原因が分からず、本人がひたすら耐えているだけになってしまいます。
(次回に続きます)
中高校生の頭痛・腹痛 ~よくなるためには?~ その2 2025/08/03
(前回の続きです)
こういう風に医療機関に行っても原因がハッキリしない場合、整骨院での治療を考えてみてもよいのではないかと考えています。
整骨院というと、足や腰に痛みのある中高年が行くところというイメージがあるかもしれません。
事実、中高年の患者は多いです。
また若い人だとスポーツをやっている人が行っているというケースもあります。
ただ、今回述べたように突発的な頭痛・腹痛がたびたびある場合にも、整骨院での治療は有効であることがあります。
例えば、うちの娘は過敏性腸炎の症状がありました。
ストレスなど精神的な要因もあったのだと思います。
医療機関に行ってもなかなか改善しませんでした。
そうしたとき、整骨院に行って骨盤矯正をしてもらう等の治療を受けた結果、症状は随分と改善していきました。
わたしも、整骨院で、腰痛・耳鳴りの症状の治療を続けています。
娘の場合、わたしと比べると、症状改善のスピードはかなり速いです。
年を取っていけば、「悪い原因の蓄積度合い」は、若い人に比べてよほど多いからです。
若い方の改善スピードは、こちらから見ていて、ホントにあっという間という感じです。
まあ、これは致し方のないことですが。
(次回に続きます)
中高校生の頭痛・腹痛 ~よくなるためには?~ その3 2025/08/04
(前回の続きです)
骨盤矯正など整骨院での治療は、健康保険の適用外です。
そのため治療費は高くなります。
整骨院での治療は、いわゆる原因療法です。
病状の原因となっているものを根本から治していくという考え方です。
具体的には、
「歪みのある体を正常に近づけていって、病の根本となるものを取り除く」
というコンセプトの下に治療が行われます。
家屋に例えれば、柱や梁を直していくという考え方に近いです。
そのため、時間もかかります。
この点、対処療法とは違います。
対処療法は即効性がありますが、原因そのものが改善しているわけではありません。
ちなみにわたしが重度の腰痛を治療してもらったときには、約2年ちょっと、治療費も車1台分くらいかかりました。
でも、腰痛で苦しんでいたときのことを思うと、おカネには代えられません。
治療していただいて、今もありがたかったと感じています。
もし中高校生の中で、突発的な頭痛・腹痛が悩みの種になっているのなら、一度、整骨院での治療を検討してみてもいいかもしれません。
その際は、「骨盤矯正」をメインテーマにしている治療院を勧めたいです。
というのも、わたしはその治療で症状が改善したからです。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
受験学習の目的は「次からのテストで間違えないこと」! その1 2025/08/05
生徒さんを学習する様子を見ていると、わたしなりに感じることがいくつもあります。
その中で、今回取り上げたいのは、
「次からのテストで間違えない」と考えている生徒さんは非常に少ない
という点です。
例えば、指導中にしても、課題にしても、生徒さんからは
「できるだけ早く、目の前にある課題・取り組むべきことから解放されたい」
という気持ちだけはビンビンと伝わってきます。
なんだか思わず苦笑してしまいそうになります。
そういう気持ちを、さすがに彼らは口にはしません。
しかし、表情・答案などを見ていると、彼らがどういうことを考えて学習に当たっているかが見えてしまいます。
あまりにもハッキリ見えて、嫌になってしまうほどに。
そんなわけで、特に指導中には、いま取り組んでいることがどういう意味を持つのか、できる限り繰り返し伝えることにしています。
・・・いま、あなたのやり方を見ていると、大切なところが抜けてますね。
答え合わせにしても、問題を解くときにしても、その目的は
「次からのテストで間違えないようにする」
ためです。
やった後、「後は野となれ山となれ」では成績を上げていくことは難しいんですよ。
(次回に続きます)
受験学習の目的は「次からのテストで間違えないこと」! その2 2025/08/06
(前回の続きです)
彼らが所属している部活動...
野球部でも、吹奏楽部でもいいですが...
そこで同じミスを、同じように、何度も繰り返していたら...
たぶん、顧問の先生や監督さんから、それ相応のお叱りを受けるのではないでしょうか。
彼らも、部活動中なら、
「さっきはあのやり方で空振りしちゃったから、今度はこうやって、確実に当てていくようにしよう」
などと、ちょっとくらいは考えるのではないでしょうか。
周りの人たちの目もあるでしょうし。
そうした環境の中で、さして難しくないようなものを、同じように、何度もミスするとすれば、
「あいつ、何やってんの?」
と、同じ部活に所属している生徒さんたちに思われたりもするでしょう。
ところが、彼らの本分たる学習の段になると、これがさっぱり通用しなくなります。
同じミスを、同じように、何度も繰り返します。
わたしも職業柄、彼らの学習状況には、だいぶ耐性やら免疫が付きました。
まあ、部活動は彼らが選んでやってはいます。
部活動のほうが、やっていておもしろいのでしょう。
そういう違いがあるのは確かなのですが...
ただ、それにしても...という気は否めません。
(次回に続きます)
受験学習の目的は「次からのテストで間違えないこと」! その3 2025/08/07
(前回の続きです)
そんなこんなで、わたしは何を言いたいのか。
伝えたいことは、
「次からのテストで間違えない」と考えている生徒さんはライバルを出し抜ける確率が高い
こういうことです。
さすがにトップ層では、こういう考えだけでライバルを出し抜くことは難しいでしょう。
しかし、準トップ以下の層が、普段からこのような心構えでいるとどうなるか...
目標とする学校に合格できる確率は、かなり高くなると考えられます。
なぜなら、準トップ以下の層は、「次からのテストで間違えない」と考えている生徒さんが、ガクンと減るからです。
そもそもの能力が高いとは言えない生徒さんであっても、「次からのテストで間違えない」と考えながら学習しているかどうか、こちらはすぐに見抜きます。
そして、そういう生徒さんは、確実に第一志望校に合格していきます。
彼らの周りが、今まで申し上げた状況ならば、その結果も当然と言えます。
入学試験というのは、だいたい同じくらいの成績層の受験生が競い合います。
中学の定期試験で200点(1科目30点くらい)を取る生徒さんは、450点以上(1科目9割)を超す生徒さんのグループと、入試で競うことはありません。
ここが肝になります。
「モンスターペアレント」一考 ~お陰様でよいご父兄に恵まれています~ その1 2025/08/08
今回のコラムでは、上記のツイートをもとに話を進めます。
話題は、いわゆる「モンスターペアレント」についてです。
先ほど引用したケースについては、先生が生徒に下した措置が、厳しいか、そうでないかという点の議論は確かにあるかもしれません。
しかし、学校側としては特に教育の範囲を逸脱するようなことがあったわけではありません。
わたしには、ここで顔出しをして記者会見をしている人物が、いわゆるモンスターペアレントに見えました。
ごく控えめに言って、くだんの父親は、わたしの常識とは違う世界にお住まいの方です。
学校のほうも大変です。
翻って、わたしの場合、お陰様で自分のブランド(というほどのものでもありませんが)を立ち上げて以来、ご家庭・ご父兄には随分と恵まれてきました。
家庭教師派遣会社を通じて生徒さんを紹介していただいたときに比べると、これは心からそう思います。
一般論として、当方にお申し込みくださるご父兄は、コラムを含むホームページ、YouTube動画、Twitterなどを十分にお読み・ご覧いただいています。
そうした上でご連絡をくださる方がほとんどです。
そういうプロセスがあるおかげか、指導には実にスムーズに入れます。
(次回に続きます)
「モンスターペアレント」一考 ~お陰様でよいご父兄に恵まれています~ その2 2025/08/09
(前回の続きです)
ただ、モンスターペアレントまではいかないが、「ちょっとアレ」という方はごく少数ながらいらっしゃいました。
こういう方というのは、一定数いらっしゃるようです。
本欄をお読みのご父兄も、思い当たるのではないでしょうか。
職場に行けば、モンスターそして「ちょっとアレな方」と日々に接しているというケースは多くないと思われます。
この「ちょっとアレな方」というのは、面談してみるとよく分かります。
そういう方と面談をしているとき、
「ああ、たぶんこのご家庭の案件は長く続かないなあ~
自分の予感が外れてくれるといいんだけどなあ~」
などと思いながらいるわけです。
しかしながら、不幸にして、この種の予感は確実に当たってしまいます。
そして、こうした「ちょっとアレな方」のご家庭の生徒さんというのは、なぜだか「とてもいい生徒さん」なのです。
わたしが「この生徒さんのためにしっかり教えたい!」と思うような生徒さんばかりでした。
「当初の予想通り、このご家庭は、最初からああいう感じだったから長く続かなかった...
でも、生徒さんはいい生徒さんだったなあ~
教えていきたかったなあ~」
というのが、偽らざるホンネです。
(次回に続きます)
「モンスターペアレント」一考 ~お陰様でよいご父兄に恵まれています~ その3 2025/08/10
(前回の続きです)
いわゆるモンスターペアレントであるとか、「ちょっとアレな方」は、わたしからすると「契約が切れてしまえば終わり」です。
こちらは、「生徒さんを指導をして、その対価を指導料としていただく」という営利企業です。
この点、学校とは性格が違います。
前回お伝えしたとおり、そのようなご家庭を長く指導するということはありません。
だいたいはあちら様のほうから去っていきます。
しかし、学校の場合、「あちら様のほうから去っていく」というハードルは高いです。
今回、話題になったのは高校での出来事です。
義務教育ではない以上、「あちら様のほうから去っていく」ことも理論の上では確かに可能です。
また、「そんなにご不満なら、うちの学校には来ないでください」と語ることも、理屈の上ではできます。
が、実務上はなかなかそういう訳に行きません。
そういう点、学校の先生は大変だと思います。
いくら先生の指導に大きな問題はなかったとしても、報道自体が全国に拡散されてしまっては、先生の心労も大きいです。
この「拡散」のスピードが、30年前や40年前と今とでは、桁違いです。
おまけにネットはずっと、騒動の痕跡が残り続けてしまいます。
ううん...
「え? わたしが教育者? それは学校の先生方に失礼です」 その1 2025/08/11
この間、Twitterに流れてくるタイムラインを見ていました。
すると、塾を運営している方のツイートが目に留まりました。
そこには、あらまし次のようにあります。
・・・自分は、Twitterで、とある人物から
「あなたは教育者であるはずなのに、利益がどうとかそういうことを口にしていいのか」
ということを言われた。
そもそも自分は教育者だと思っていない。
利益を出さなければ生活ができないのだから、それを言うのは当然だ。
これに関しては、わたしもおおむね同じ意見です。
今回のコラムは、先ほど紹介したツイートに、わたしの考えるところを補っていきます。
まず、わたし自身は、自分のことを「教育者」と思ったことは一度もありません。
わたしがそう思うことは、学校の先生など「本物の教育者」の方々に失礼です。
ただ、その一方で、ご父兄や生徒さんにとって、指導をしている間、わたしは「先生」でしかないわけです。
そう感じない方がいらっしゃるかもしれませんが、それはかなり少数です。
それゆえ、ご父兄や生徒さんの前では、柄にもなく教育者然として振る舞わなくてならない...
こういう趣旨のもと、本人なりに自省をして指導に臨んでいます。
(次回に続きます)
「え? わたしが教育者? それは学校の先生方に失礼です」 その2 2025/08/12
(前回の続きです)
さらに前回述べた
「あなたは教育者であるはずなのに、利益がどうとかそういうことを口にしていいのか」
という指摘?苦情?については、全く当を得たものではありません。
学校の先生のような、「本物の教育者」は、公立学校勤務の場合、公務員です。
私立学校の場合は学校に雇用されてはいます。
そして、私立学校には「補助金」という形で、税金が投入されています。
一方、学習塾等は、ご父兄から頂戴した授業料で運営をしています。
お上から「補助金」を頂くなどということは、基本的にありません。
それはスーパーマーケットや個人のラーメン屋などとベースは同じです。
学校の先生が「利益がどうのこうの」を口にしないのは、そういうことを気にしなくてもよい勤務体系になっているからです。
その点を理解しない、あるいは理解しないふりをして苦情をいうというのは、全くもっておかしな話です。
苦笑するほかありません。
まあ、ただ、世の中にはおかしなことを言ってくる人たちは一定数います。
twitterなどSNSで発信するとすれば、そういう「不愉快さ」もついて回るということを認識しておく必要がありそうです。
なお、当コラムは16日まで「夏期休業」となり、休載します。
17日から再開します。
よろしくお願いいたします。
公立高校入試システムはこう変わってきました その1 2025/08/17
この前、当コラムで、ラサール石井参院議員の発言を取り上げました。
<関連コラム>
今回は、上に示した<関連コラム>に加える形でお伝えいたします。
中心とするテーマは、公立高校入試システムが、どのように変わってきたのかです。
今、宮城県で行われている公立高校入試システムは、大きく変わったり、マイナーチェンジがあったり.....
ということを重ねてきました。
今の公立高校入試システムというのは、「こうしたほうがいい」という箇所は確かにあります。
わたしもこの「改善すべき点」については、大いに思うところがあります。
しかし、同業の方のお話や、現場の先生方のお話を聞くと、今のシステムは、まずます受け入れられているように思います。
6年前まで行われていた制度は、高校・中学の教育現場、受験産業界隈から、随分と大きな苦情がありました。
それを改めて以来、入試システムに対する批判はかなり少なくなっています。
(次回に続きます)
公立高校入試システムはこう変わってきました その2 2025/08/18
(前回の続きです)
公立高校の入試制度は、年を経て変わってきました。
「入試制度」といっても、その意味するところは多方に広がります。
ここでは「入試というテストそのもの」に絞ります。
ここ50年での変化は次の通りです。
(1)内申点+ペーパーテスト
→3月に実施
(2)「内申のみで決まる推薦入試」
→2月に実施
「内申点+ペーパーテスト」
→3月に実施
(3)「内申点+ペーパーテスト」
→2月・3月に2回実施
(4)内申点+ペーパーテスト
→3月に実施
これを見ると、(1)→(2)→(3)→(4)一周回って同じところにたどり着いています。
となると、途中の(2)(3)というプロセスは何だったのでしょう?
しかも今のシステムがそれなりに支持をされているのです。
ということは、この50年間、「内申点+ペーパーテスト」3月実施で一発という制度を変える必要がなかったという話です。
この漫画のようなお話を手短に言えば、
そのときどきの偉いさんたちの「改革」という名の「気まぐれ」で、現場が混乱した
こういうことになります。
こういった場面を目にしているわたしとしては、眉に唾を付けながら、入試に関するお上の「改革」をつぶさに眺めるという習性ができてしまっています。
(次回に続きます)
公立高校入試システムはこう変わってきました その3 2025/08/19
(前回の続きです)
世の中にある制度で、「完璧」なものはありません。
そしてその制度の下では、必ず得をする人たち・損をする人たちができます。
受験制度もその宿命から逃れられません。
さらに受験制度は、次の2点が求められます。
・できる限り分かりやすくシンプルであること
・現場の負担が軽いこと
そうした意味で、「内申点+ペーパーテスト」3月実施で一発試験というのは、シンプルで分かりやすいのです。
一時期、「内申点+ペーパーテスト」2・3月の2回実施という制度になっていたことがあります。
これは、現場の負担が非常に重く、苦情の多かった制度でした。
試験を2回実施したのは、一発入試で力の出せない受験生に対する配慮です。
そのため、複数回の受験機会をお上は与えました。
これはお上なりの「優しさ」の発露です。
しかし、「優しさ」は現場の過重負担を引き起こしました。
そうなると、「昔のほうがよかった」ということになります。
公立高校の入試制度が、50年近くもさまよい続けて、昔の制度に近い形になったのも、
「そりゃあ、そうだよな」
という感想しかありません。
今後、入試制度が改まるにしても、「シンプル」「現場の軽負担」という側面は忘れずに「改革」してほしいものだと思わずにはいられません。
広陵高校の甲子園辞退に思う ~野球名門校と受験名門校の差~ その1 2025/08/20
甲子園大会で広陵高校が大会の途中で出場を辞退しました。
これが、ニュースとして大きく取り上げられています。
原因は、野球部内での暴力事件にかかわる不祥事が表沙汰になったことです。
報道によれば、この事件については、今回のことだけではなさそうです。
深い闇があります。
そのようなことを踏まえたうえで、今回の広陵高校の騒動を、「受験関係者」という視点で見ると、次のようになります。
結局、学校ってまずもって勉学をやる場所なんだよなあ~
スポーツは二の次...
広陵高校は「野球名門校」です。
一方、わたしは職業柄、「受験名門校」の情報に接することが多いです。
以下、「野球名門校」特にスポーツ推薦で高校に進むケースを、「受験名門校」と比べながら、語っていきます。
わたしの考えとしては、「野球名門校」へスポーツ推薦で行く生徒さんたちというのは、
「苦労の割には立場が弱い」
というものです。
「野球名門校」というと、全寮制というところが随分とあるようです。
そこでは生活をしていく上で、いろいろな制限があります。
「普通の高校生」よりは、よほどストイックな生活を送っています。
何しろ、広陵高校の野球部には、カップ麵を食べる自由がないのです。
(次回に続きます)
広陵高校の甲子園辞退に思う ~野球名門校と受験名門校の差~ その2 2025/08/21
(前回の続きです)
結局、学校ってまずもって勉学をやる場所なんだよなあ~
スポーツは二の次...
わたしは前回に、このように書きました。
このことを強く感じるのは、「野球名門校」の球児たちの「卒業後」です。
彼らはその後に大学進学をしたり、専門学校に行ったり、就職したり、さまざまでしょう。
ただ、いずれの場合にしても、「推薦」を受けて、進むのが相当数に上ります。
そして、その場合の「推薦」は、監督が大きな権限を持っています。
「野球名門校」の監督ともなれば、「卒業後の進路」に関しては、進路先とツーカーです。
こういう現状を言い換えると、彼ら「野球名門校」の球児たちの生殺与奪の権限は、監督に握られています。
それは、在校中も卒業時もです。
一方で、甲子園への出場が決まっても、チームメイトが不祥事を起こせば、出られなくなってしまいます。
球児本人が不祥事に関わっていなくても。
いくら彼らがすごい選手であっても。
甲子園出場を目指して、小さいころから頑張ったのにもかかわらず、自分でどのようにもできない理由で、夢がパーになってしまうのです。
これでは泣くに泣けません。
前回のコラムで、
「苦労の割には立場が弱い」
と書いたのは、そういう理由からです。
(次回に続きます)
広陵高校の甲子園辞退に思う ~野球名門校と受験名門校の差~ その3 2025/08/22
(前回の続きです)
「受験名門校」の生徒たちは、小さいころから塾通いをしています。
これは、「野球名門校」の球児たちが、小さいころから野球のクラブチームに入っている事情と似ています。
しかし、「受験名門校」の生徒たちは、全寮制というわけでもありません。
もちろん、寮になっているところは、何かと制限があるでしょう。
が、新入生にはカップ麺を食べる自由がないなどというのは、聞きません。
ましてやカップ麺を食べて、先輩からボコボコにされるという話も聞きません。
同級生が不祥事を起こして、自分の東大受験ができなくなることもありません。
学校の先生が卒業後の進路に対して、生殺与奪の権限を握っているなどということもありません。
「受験名門校」で、大学受験をし、結果を出すのは、生徒個々人です。
一方、「野球名門校」では、甲子園に出て、結果を出すのは、チームです。
一人で野球はできません。
「受験名門校」の生徒のほうが、「野球名門校」の球児より、生活全般において、よほど緩やかです。
「野球名門校」の球児は、「受験名門校」の生徒に比べて、信じがたいほど大変で、制限の多い生活を送っています。
(次回に続きます)
広陵高校の甲子園辞退に思う ~野球名門校と受験名門校の差~ その4 2025/08/23
(前回の続きです)
それでいて、「野球名門校」より、「受験名門校」のほうが、社会的には評価されるという「現実」があります。
また、勉強がずば抜けてよくできて、野球も同じくらいずば抜けてできたら、たぶんその生徒は、「受験名門校」を選ぶでしょう。
そういうことを考えると、
「野球名門校」の球児って、意外と割に合わない
それに比べて、「受験名門校」の生徒は恵まれている
このように思います。
いま、わたしが述べたようなことは、たぶん、どなたも何となくは分かっていることです。
小さいころから「受験」に照準を当てて努力をしてきた生徒は、かなり恵まれた環境にいます。
「野球」だけをやってきた生徒に比べれば。
しかも、「野球」志向の生徒に比べると、よほど家庭生活・学校生活は、全般的によほど緩いです。
そうしたことを考えると、「受験名門校」を目指して、小さいころから「勉強、勉強、塾通い」というスタイルは、必ずしもマイナスにとらえる必要はないです。
小さいころから、「野球、野球、甲子園」でやってきた...
甲子園に出た...
チームメイトの不祥事で、泣く泣く辞退した...
こういう生徒も現実にいるわけですから。
以上は、ひとりの受験関係者からの見方です。
さて、本コラムをお読みの方は、どうお考えでしょうか?
中1理科という「難関」〜高校入試のハイライト〜 その1 2025/08/24
今日のコラムは、中学理科の話です。
中学理科というと、国数英のような主要教科に比べて、受験関連の話題になることは多い感じではありません。
ただ、意外と盲点になる部分があります。
それは
「中1理科はけっこう難しい」
ということです。
中1というと、ついこないだまでは小学生だったわけです。
そういうことを考えると、中1理科は随分とハードだと思います。
わたしが難しいと考えるのが、
・音・光・浮力などの物理分野
・地層などの地学分野の一部
この2単元です。
ただ、これらは中1でも後のほうに出てきます。
そういう意味で、まだ幸いともいえるでしょう。
これらの単元の難しさというのは、
「単に暗記してどうにかなるものではない」
という内容の多さにあります。
例えば、そこには計算問題も含まれます。
小学校で小数が苦手な中1生は、まずそこでハジかれてしまいます。
さらにそこでは、
「イヌが西を向くと、尾はどちらの方向を向くでしょう?」
というような「論理的な思考力」も問われます。
「イヌが西を向くと...」というのは、もちろん、あくまで例えです。
実際に出てくる問題は、もっと複雑で、かつ難しいです。
(次回に続きます)
中1理科という「難関」〜高校入試のハイライト〜 その2 2025/08/25
(前回の続きです)
前回のコラムで取り上げた「中1理科の難物分野」は、いま書いたように難しい単元です。
この点で、高校入試として気を付けておかなくてはならないことが二つあります。
第一点目は、それが高校入試によく出る分野であることです。
第二点目は、学校で中1の授業として扱ってから、高校入試を受ける中3の終わりまでに、時間がかなりたってしまっているということです。
出題するほうの側からすると、「難物分野」ということであれば、当然に入試に出す気をそそられるわけです。
というのも、そこで受験生の間に差がつくからです。
試験というのは、受験生間でほどほどに差がつかなくてはいけません。
優しすぎる問題や難しすぎる問題ばかりでは、受験生を選抜する側の高校としては困るわけです。
それから、「中1理科の難物分野」を習うのは、中1のときです。
入試として出されるのは、中3の2月・3月という時期です。
そのため、中1で授業として扱い、定期試験を受けてから、約2年間のブランクがあります。
この間、「中1理科の難物分野」は、多くの生徒さんの記憶から抜けていってしまいます。
これが受験としては、困った点なのです。
(次回に続きます)
中1理科という「難関」〜高校入試のハイライト〜 その3 2025/08/26
(前回の続きです)
高校受験には、英語や数学でも中1分野のものは出ます。
しかし、英語・数学のように「積み上げていく教科」の場合、中3の分野が分かるということは、中1の分野もほぼ理解できていることを意味します。
例えば、2次関数の問題、あるいは三平方の定理といった図形の問題ができていれば、中1の計算問題の理解もまずまずOKということになります。
英語であれば、なおのことそうです。
しかし、理科・社会といった教科は、英語・数学のような教科とは違います。
社会であれば、中1で習う縄文時代と、中3で習う大正時代以降とは、「断絶」があります。
「大正時代のことが理解できていれば、縄文時代のことも理解できている」などということはありません。
社会の場合、「難物分野」としては、歴史の近現代史、すなわちペリー来航以来の歴史が挙げられるかもしれません。
ただ、この分野とて、「中1理科の難物分野」ほどの難しさはないように感じます。
ペリー来航以降の歴史の場合、歴史上の出来事の暗記・記憶の学習が大きな意味を持ちます。
暗記・記憶をした上での高得点です。
一方、「中1理科の難物分野」は、暗記・記憶だけではどうにも太刀打ちできません。
(次回に続きます)
中1理科という「難関」〜高校入試のハイライト〜 その4 2025/08/27
(前回の続きです)
この「中1の難物分野」に関して、平均点まで行かない生徒さんは、ほぼ太刀打ちできません。
そのため、入試となれば、仮にそこができなくても、合格はできます。
もっとも目指す高校の難易度によって、確実に得点しておくべきものはありますが。
翻って、偏差値55以上の高校、泉・宮城野高校以上のところを目指そうと思えば、「難物分野」の対応を迫られます。
ことにナンバースクール志望の受験生は、「中1理科の難物分野」で「分からないところがない状態」にしておかなくてはなりません。
これがなかなかに大変です。
この「中1理科の難物分野」は、中1から中3の間に、模擬試験で出題されては来ています。
その間、学習したことを忘れないように、そして入試レベルの問題でも対応できるように、力を持ちこたえていく必要があります。
その昔、わたしが中学生のころには「難物分野」が抜けていかないように、1週間のうちに曜日を決めて「メンテナンス学習」をやっていました。
それなりに効果はあったと思います。
中3生向けの塾では、今くらいの時期から、入試対策向けに、「中1理科の難物分野」を含めた全範囲の演習を行っていきます。
それが入試まで続きます。
年々早くなる大学入試 〜高校はどう考えている?〜 その1 2025/08/28
「少子化」
「出生率低下」
・・・早い話、若い人が年を追うごとに減っていっている
こういう日本の現実に関して、本コラムをお読みのご父兄は十分すぎるほどにご存じかと思います。
そうした流れは、入試にも当然に影響を及ぼします。
その潮流の一つとして、
「難関大学が推薦・AO入試で取る学生の割合を大きくする」
という方向にシフトして行っています。
例えば、東大は「推薦入試の出願枠を増やす」ということを、公式に発表しています。
東北大に関しては、「2050年までに一般入試を全廃する」とまで宣言しています。
東北大がここまで言うのは、大胆というか、正直というか、わたしとしては、曰く言い難い気分です。
これら大学発表の意味するところは、
「優秀な受験生の青田買いを更に進める」
ということです。
こうした大学の推薦・AO入試は11月くらいから始まります。
受験生とすれば、志望大学への切符は、できる限り早く入手しておきたいと考えます。
受験生の心理と、大学の思惑が一致して、「推薦・AOという青田買い」が行われます。
そうした状況を高校側はどう受け止めるか。
・・・これまで以上に入試対策は早めに
こうなります。
(次回に続きます)
年々早くなる大学入試 〜高校はどう考えている?〜 その2 2025/08/29
(前回の続きです)
このところの少子化で、生徒さんのレベルは二極分化がより大きくなっています。
「できる生徒は、よりできるようになった」
「学習苦手な生徒は、更に苦手になった」
こういう現象です。
もちろん、ご父兄が現役学生のころから、できる生徒と学習苦手層の差というのはありました。
今は、更にその差が大きくなってきています。
真ん中がかなり少なくなっている印象です。
少子化の影響で、一人の子供にかけることのできるお金は多くなります。
そうなれば、小さいころから塾通いをする生徒が、ご父兄の時代に比べて多くなります。
できる生徒がよりできるようになっている背景には、そうした事情も原因となっています。
そのような事情を反映してか、「共通テスト」は、共通一次やセンター試験のころより、難しくなっています。
・・・大学入試のスタート時期は早くなっている
・・・難関大学の問題は難しくなっている
名門と言われる高校としては、そうした入試に対応していかなくてはなりません。
そういった流れは、学校のカリキュラム・年間スケジュールに影響を及ぼしてきます。
現状、そういう流れがあること、知っておいていただきたいと思います。
指示に従えなくなってきた子どもたち その1 2025/08/30
このところ、Twitterなどで、学校の先生あるいは学習塾・各種習い事の先生のつぶやきを見ていて、気づくことがあります。
それは、授業のときの生徒さんの反応についてです。
一つ一つの反応が、以前に比べて、遅くなっていると仰る方がいらっしゃることです。
しかも、複数の方々です。
例えば、授業で
「「◎◎ページを開いてください」
という指示を出したとします。
そのとき、クラスの中には、反応の早い生徒さん、早くない生徒さん、様々にいるわけです。
それで、クラス全体として、そういう指示を出してから、だいたいの生徒が「◎◎ページを開く」までの作業を終えるまで、その昔より時間がかかるようになったというのです。
わたし自身、そうしたことを感じたことはありません。
個別の指導、そして、学習の苦手層を多く担当してきたから、そういった「時代のギャップ」を感じなかったのかもしれません。
あるいは、わたしが単に鈍感なだけとか...
いずれにしても、生徒さんの反応の遅さが昔と比べてどうだとかいうことが気になったことはありません。
ただ、複数の先生方が
「以前に比べて、反応の遅い生徒が増えている」
というのは、ちょっと気にかかります。
(次回に続きます)
指示に従えなくなってきた子どもたち その2 2025/08/31
(前回の続きです)
「生徒さんの反応が昔に比べて遅くなった」
このように先生方が感じる理由は、いくつか考えられます。
・実際に遅くなっている
・実際には遅くなっていないが、先生方がそう感じているだけ
正直、どれが正解なのか、わたしは分かりません。
ただ、割とハッキリしていることがあります。
それは、
「できる生徒とそうでない生徒の差がこれまで以上に大きくなってきた」
ということです。
普通、「できる生徒」は、学習面でできることを意味します。
しかしこうした学習面での習熟度の差が、学校生活のちょっとしたことにも影響している可能性があります。
それから、学校現場では、昔に比べて「厳しい指導」「きつい指導」が段々となされなくなってきたという面があるのかもしれません。
例えば、学校の宿題一つとっても、そうです。
宿題をやってこないため、罰を受けたり、先生から口うるさくやるように指導されるという機会は、相当に減っているようです。
「できる生徒」はともかく、「そうでない生徒」にしてみれば、宿題をやっていかなくても何も言われないなら、どうなるでしょう。
やらずにいる、と考えるようになっても不思議ではありません。
以上のような風潮が、生徒のちょっとした反応の遅さに、もしかしたらつながっているのではないでしょうか。
ご利用案内 リンク
お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ
<電話での受付>
15:00~20:00
※日曜日は除く
※電話は
「雅興産(みやびこうさん)」と出ます
成績upのヒント!
教育コラム「雨か嵐か」
プロ家庭教師菊池
住所
〒981-0933
仙台市青葉区柏木1-2-29-301
電話受付時間
15:00~20:00
定休日
日曜日