〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-29-301
電話での受付:15:00~20:00
定休日:日曜日
小学校の先生方へ! 「教えていない」やり方で問題を解いた生徒を褒めてあげて下さい! その1 2019/09/01
以下は、ツイッターで少し触れた内容です。
先日、小学生に中学受験の指導をしていて、「これは困ったもんだ.....」という場面に遭遇しました。
その小学生では、「自主勉」の課題というのがあります。
「自主勉」では、何でもいいから、ノートに自分のやった勉強を書くように言われているそうです。
そこでわたしは、「じゃあ、中学受験の問題集、やって行っては?」と提案しました。
すると、その生徒さんは、
「学校で習ってないことをやって行くと、先生に怒られる。
学校でやっていないやり方で算数をやると、先生に怒られる」
と言うのです。
そんなわけで、「先生に怒られないような」課題を、「先生に怒られない」やり方でやって行くというのです。
それを聞いて、わたしは深く溜息をつきました。
それから深く失望しました。
そこで、わたしは生徒さんにこう言いました。
「わたしが担任の先生なら、中学受験の問題集を解いていっても怒りませんよ。
『学校でやっていないこういう方法を知ってるのか! すごいなあ!』って褒めますよ」
そういうと、その生徒さんは、「へえ〜そうなんだ」という驚いた表情を見せました。
そして、わたしのほうを見て、目を輝かせていました。
生徒さんにこういう思いをさせている先生って、何なんでしょうね.....(苦笑)
(次回に続きます)
小学校の先生方へ! 「教えていない」やり方で問題を解いた生徒を褒めてあげて下さい! その2 2019/09/02
(前回の続きです)
とはいえ、くだんの先生のお気持ちも分からないわけではありません。
先生の立場からすると、クラス全員が中学受験をするわけではありません。
また、今まで履修した内容をしっかり復習してほしいという気持ちもあるでしょう。
しかし、そのことと、「学校でやっていないやり方をすると怒る」ということは別です。
中学受験をする生徒さんは、他のクラスメイトが勉強していないときも、自分の力で努力して、「学校でやっていないやり方」を身につけたのです。
そういう努力は大いに評価すべきではないでしょうか?
中学受験をする生徒が、授業をまじめに聴かないとか、授業妨害をしたとか、そういうことがあった場合は、学級担任として、これをとがめるのは当然です。
しかし、「学校からはみ出した」という一点をもって生徒をとがめるがごときは、教育者として倒錯しているのではないのでしょうか?
「学校で教えたやり方でやってほしい」というのなら、ほかに言い方はあります。
「学校でやってないAというやり方で解くなんて、スゴイね!
じゃあ、最近学校でやったBというやり方で解いてみて。
これはこれで、長い目で見ると受験の役に立つよ」
このように先生がおっしゃれば、すべて丸く収まります。
わたしと違って、小学校の先生は、お上が認めたホンモノの先生です。
このくらいのことは、生徒に言えてしかるべきなのではないでしょうか?
(次回に続きます)
小学校の先生方へ! 「教えていない」やり方で問題を解いた生徒を褒めてあげて下さい! その3 2019/09/03
(前回の続きです)
実際、中学受験の算数に関して申せば、これは、極めて独特なものです。
通常、中学生の数学でやるようなことを、小学生が挑むのです。
平均的な中学生は、まず解けません。
中学受験生の努力は、ほんとうにすばらしいものです。
指導中はきっちり集中しています。
凡百の中学生より、よほど望ましい姿勢です。
わたしが小学生の頃を顧みると、己の幼稚ぶりに汗顔の至りです。
しかし、彼らにも弱点があります。
彼らは「こうすれば答えが出る」という訓練はよくしています。
しかし、「どうしてそれがそういう解法で解くと正解になるのか」ということを、彼らの多くは知りません。
そうした意味で、小学生の先生の「最近学校でやったやり方で解く」というのは、極めて意味のあることだと思うのです。
これをお読みの小学校の先生の中には、「受験屋ごときが何をほざくか」とお感じになる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、小学校の先生にとっても生徒なら、わたしにとっても生徒です。
どのように思考を巡らせてもわたしに理があるなら、小学校の先生方に物を申す権利くらいはわたしにあると認識しています。
わたしはこの権利を最大限活用し、「おかしなものはおかしい。先生のお気持ちもわかるが、このようにしていただきたい」ということを強く訴える次第です。
妄言多謝。
「動画で雨か嵐か」 〜実技教科のペーパーテストを受ける意味〜 2019/09/04
仙台東高と泉高校の英語科の違い 〜入試と教育課程〜 その1 2019/09/04
受験関連のネット空間を見ると、公立高校の理数科に比べて、英語科に関する情報は少ないように感じます。
理数科の設けられている高校は、三高・宮一・向山といったナンバースクール、あるいは準ナンバーです。
一方、東高と泉高校は、そうではありません。
そういう差のためかとも思われます。
そこで今回は、仙台東高と泉高校の英語科について取り上げてみます。
焦点を当てる話題は3点です。
(1)みやぎ模試偏差値
◎東高英語科 47
◎泉高英語科 53
(参考)
☆東高普通科 51
☆泉高普通科 56
東高の場合、普通科との差が4ポイントです。
泉高の場合、普通科との差が3ポイントです。
偏差値4ポイントというと、入試の差が約30点強です。
偏差値4ポイントというと、入試の差が約25点前後です。
30点とか、25点という差は、入試という観点からすると、かなり大きいです。
一高と二高の偏差値差が2ポイントです。
それでも難関大学の合格実績については、開きがあります。
理数科の場合、普通科と比較すると、向山が最も開きがあって2ポイントです。
宮一が1ポイント、三高が同じです。
そういう観点から見ると、英語科は普通科に比べて入りやすくなっていると言えます。
(次回に続きます)
仙台東高と泉高校の英語科の違い 〜入試と教育課程〜 その2 2019/09/05
(前回の続きです)
(2)入試方法の違い
東高英語科 面接なし
泉高英語科 面接あり
今年の春に行われた入試では、両校とも入試の実施方法に違いはありませんでした。
しかし、来春から泉高英語科には、面接が加わります。
この面接の実施要綱は県教委からの発表によると次の通りです。
◎形態・・・個人面接
◎時間・・・10分程度
◎内容
・・・(1)志望動機等(日本語)
・・・(2)口頭試問(英語)
◎配点
・・・(1)意欲・態度 30点
・・・(2)表現力(英語)等 70点
面接は受験生全員に実施します。
選抜方法としては、まず「共通選抜」という通常と同じような方式で、合格者32名を選びます。
そして、この「共通選抜」から漏れた受験生のうち、上記面接を含めた「特色選抜」で、残り8名を選びます。
泉高校英語科の「特色選抜」は次のような配点です。
内申点195
入試650(国数英を1.5倍)
面接100
ボーダーラインにある受験生を選ぶ際、この面接が物を言います。
内申点195点に比べ、面接は100点と比重は大きくありません。
が、全体を見ると、決して小さくはありません。
10分程度の個人面接というのは、相当に長い時間です。
英語の口頭試問については、どのようなものになるのか、受験生としては大きな不安材料です。
ただ、わたしが想像するに、英検3級の面接試験程度のレベルになるのではないかと踏んでいます。
この「英検3級」というのは、平均的なレベルの中3生なら合格します。
(次回に続きます)
仙台東高と泉高校の英語科の違い 〜入試と教育課程〜 その3 2019/09/06
(前回の続きです)
(3)高3における数学
◎東高英語科 選択
◎泉高英語科 必修
英語科を選択する人は、ほぼ全員が文系に進むものと思われます。
そうした中、高3になると、東高は数学を履修せず、選択教科とすることが可能です。
一方、泉高校は、高3になっても数学は必修です。
ガッチリ4時間あります。
この4時間という数字は、古典が3時間あることと比べると、比重はそれなりに大きいと言えます。
数学にこれだけの時間を割いているというのは、両校の国公立志向にも一因していると考えられます。
県の公式サイトによれば、今春の国公立進学者は次の通りです。
東高 (卒業生)272 (進学者)25
泉高 (卒業生)278 (進学者)80
国公立大学への進学者は、泉高が東高の3倍強です。
英語科といえども、国公立への進学ということになれば、数学は必要になってきます。
両校の偏差値の違いを考えると、納得できる数字ではあります。
ただ、私大文系に行く人で、数学必修でないという人にとって、泉高での数学4時間というのは重く感じるかもしれません。
参考までに、2年時の数学の時間は次の通りです。
◎東高英語科 6時間
◎泉高英語科 6時間
2年時は両校とも、「数学ガッチリ」です。
ラジオ番組出演が決定しました! 2019/09/07
表題にあります通り、このたび、ラジオ番組への出演が決まりました。
番組の概要は以下の通りです。
放送局名: エフエムなとり “なとらじ801”
周波数: 80.1MHz
出演番組: なとらじWIDE
放送日: 9月16日(月・祝)
放送時間: 13:00−15:00
☆この時間のうち、13:30ごろからの「ゲスト&Pコーナー」に約20分出演予定。
聴取方法:
☆FMラジオ:
周波数は80.1MHzです。
ただし、この電波が届くのは、名取市周辺のみです。
☆パソコン:
エフエムなとりサイトの右側にあるsimul radioのリンクから。
上記の青文字のところをクリックしてアクセスも可能です。
その際、windows mediaplayerが必要
※多くのwindowsパソコンには、mediaplayerがすでにインストールされています。
☆スマートフォン
ListenRadioのリンクから。
これにアクセスし、ListenRadioというアプリケーションソフトをダウンロードしてください。
そこを操作し、番組を聴くことができます。
(注意!)ListenRadioの画面が出るには、結構時間がかかります。
わたしのスマートフォンでやってみたら、型が古いせいもあるのかもしれませんが、LitenRadioの画面が出るまでに、2〜3分かかりました。
イライラして、途中でアクセスを辞めないようにしてください。
番組では、名取市在住の中学生およびご父兄を対象に、来春実施される公立高校入試の変更点、試験の点が上がる学習法、上手な塾・家庭教師の活用法などを話す予定です。
興味のある方は、聴いてみてください。
よろしくお願いいたします。
「この生徒さんは伸びる?伸びない?」の判断基準 その1 2019/09/08
わたしのような受験関係者は、「生徒さんに学習指導をする」そして「成績を伸ばす」ために、神経を使っています。
当然のことながら、ただやみくもに指導をしているわけではありません。
「この生徒さんなら、もう少し行けそう」
「この生徒さんは、これ以上はちょっと無理っぽいな」
などと判断しながら、最適と思われる指導を心がけています。
その際、「この生徒さんは伸びる?伸びない?」という判断はどのようにしているか、ちょっと書いてみます。
わたしの「判断基準」は、主として3点です。
(1)その生徒さんが持つ「本来の能力」
(2)菊池の指導内容がどれだけ実行できているか
(3)その生徒さんの意欲・性格
以下、詳説します。
(1)その生徒さんが持つ「本来の能力」
生徒さんの「本来の能力」というのは、平たく言えば、「親からもらった能力」です。
言い換えると、本人が努力する、しないにかかわらず、「生まれながらに備わっている力」です。
学習の結果において、この「生まれながらに備わっている力」が最も大きく影響します。
学習を進めるに当たっては、
「二高を目指すのであれば、Aという問題は、現在解けていなければならない」
「問題Bが解けて、問題Cが解けないなら、この生徒さんは、偏差値40前後くらいかな?」
というような「基準」が存在します。
それに基づき、上記(2)(3)と合わせながら、「現在の能力」と「本来の能力」を判断しています。
(次回に続きます)
「この生徒さんは伸びる?伸びない?」の判断基準 その2 2019/09/09
(前回の続きです)
「現在の能力」と「本来の能力」は異なります。
だいたいの生徒さんは、「本来の能力」が「現在の能力」を上回ります。
これは言い換えると、ほとんどの生徒さんの場合、「何がしかの伸びしろがある」ということです。
また、「本来の能力」と「現在の能力」の差が、かなり大きいという生徒さんがときどきいます。
いろんな理由、本人の怠慢あるいはよい指導者に巡り会わなかった等で、十分な力を発揮しなかった生徒さんです。
「本来の能力」と「現在の能力」の差が大きい場合、本人が勉強をしだすと、平均的な生徒さんより短い期間で伸びを示すことがあります。
塾等で「短期間にこれだけ伸びました!」という見出しがつくのは、だいたいこのケースです。
わたしもそうした生徒さんを担当したことがあります。
留意をすべきは、「現在の能力」が「本来の能力」を上回ることがないということです。
東大理Ⅲ合格者と同じ勉強をやったところで、誰もがそこを突破できるというわけではありません。
「現在の能力」を「本来の能力」にできうる限り近づけることができるだけです。
指導者のいうことをそのまま実践し、なおかつそれ以上に成績が伸びないなら、これは、その人の能力の限界です。
どんなに優秀な指導者でも、それ以上の指導はできません。
(次回に続きます)
「この生徒さんは伸びる?伸びない?」の判断基準 その3 2019/09/10
(前回の続きです)
(2)菊池の指導内容がどれだけ実行できているか
これは非常に重要です。
成績向上のためには、わたしの指導内容を生徒さんが実践する必要があります。
指導内容にも、高度なものと、そうでないものがあります。
学習の苦手な生徒さんは、わたしの指導内容を実践するまでに、かなりの手間がかかります。
まず、本人に指導内容を積極的に実践してみようという気持ちがかなり欠けています。
当座の間は指導内容を実践するものの、「元の自分のスタイル」に戻ってしまうことも、ままあります。
また、能力の高い生徒さんであっても、我流に執着するというケースもあります。
受験関係者が言う「素直さが足りない」生徒さんです。
そうした生徒さんは、「本来の能力」を発揮できません。
わたしはどちらかと言うと、生徒さんに「菊池スタイル」を押し付けたいほうではありません。
指導時には、どうしてそういう指導が必要なのかを、懇切丁寧に説明します。
また、生徒さんが「オレ流」をやっていて、きちんと結果が出ているのなら、これを容認しています。
しかし、「オレ流」が、間違いを引き起こす原因になっていれば、それは認めません。
ところがそうしてなお、「オレ流」に拘泥する生徒さんがいます。
そういう生徒さんは「伸びないな〜」と判断しています。
(次回に続きます)
「この生徒さんは伸びる?伸びない?」の判断基準 その4 2019/09/11
(前回の続きです)
(3)その生徒さんの意欲・性格
生徒さんの意欲というのは、例えば「○○高校に入りたい」というのが、どれほど強いかということです。
だいたい誰でも、志望校に入学したいという気持ちはあります。
しかし、その気持ちがどれほどなのかは、各人各様です。
当然のことながら、そういう意欲の強い人は、伸びが期待できます。
この意欲というのは、その生徒さんの性格とも関係します。
ただ、「意欲の強い人=オレがワタシが、という意識の強い人」というわけではありません。
性格的におっとりしていても、意欲の強さは十分に感じられる生徒さんも少なくありません。
逆に、「オレが!ワタシが!」という生徒さんであっても、勉強をきちんとしていない、という人もいます。
こういうケースでは、前回のコラムで述べた「素直さが足りない」と評される場合が多いです。
受験関係者にとっては、いちばん手がかかるタイプです。
当然の帰結として、そういう生徒さんは成績の伸びが期待できません。
わたしは、以上3点を中心に、「この生徒さんは、伸びるか、伸びないか」を判断しています。
ほかの受験関係者の方はどのようにしていらっしゃるのか分かりませんが、たぶん、わたしと大きくは違わないと思います。
「動画で雨か嵐か」 〜用語記憶のコツ 〜字の意味を考える〜 2019/09/11
学年最低を取ってしまった技術家庭科の期末試験(涙) その1 2019/09/12
9月4日に、動画「実技教科のペーパーテストを受ける意味」をアップしました。
これは、とかく面倒だと考えがちな実技教科のペーパーテストを受ける意味は那辺にあるのか、ということを述べたものです。
動画では、実技教科の知識も、のちのちの受験のことを考えると、「知っておいて損はない」という結論になっています。
このような動画を発表しましたが、以上のメッセージは、実のところ、中学生時のわたしに語り掛けているようなところが半分ほどあります。
本来なら、わたしは偉そうなことを言えた義理ではありません。
というのも、わたしは、中学2年生だったと思いますが、技術家庭科の定期試験で「学年最低」を取ってしまった経験があるからです。
そのときの単元は、金属加工だったか、木工細工だったか、どちらかだったと思います。
期末試験の勉強をしようと、試験の数日前にワークブックやら、ノートやらを見返しました。
が、どうも素直に頭に入って行きません。
「何だか難しい単元だな〜」と思いつつ、返ってきた答案を見ました。
45点だったか、44点だったか、そういう点数が付いています。
ちなみにその点数は100点満点です。
当時、わたしたちは、男子だけに技術の授業がありました。
女子は家庭科だけです。
そんなわけで、技術の試験を受けたのは、男子だけでした。
(次回に続きます)
学年最低を取ってしまった技術家庭科の期末試験(涙) その2 2019/09/13
(前回の続きです)
答案が返ってきたときには、「随分とこれは、やらかしちゃったな.....」と感じました。
自分としては、まるっきり勉強をやらなかったわけではありません。
何しろ、主要5教科のことで頭がいっぱいでした。
とはいえ、自分なりにはやったつもりでした。
しばらくして、期末試験の分布表が渡されました。
技術科の分布を見ると、60点台から上の人たちがかなりいます。
講評には「今回の試験は割と定着のよかったところで.....」とあります。
結果は、40点台が1名で、0〜30点台を取った生徒はゼロです。
「エ? オレって学年最低だったの?????」
そう思って、3度ほど見返しました。
やはり学年最低でした(涙)
「オレって、アイツとか、アイツとかより低かったの? 一応勉強したのに?」
と、普段あまり成績のよくなかった級友を思い浮かべました。
試験には学年最高もあれば、学年最低もあります。
わたしにとって、学年最低というのは、やはり衝撃であり、ショックでした。
実技教科をなめていたわけではありませんが、しっかり取り組む必要があると痛感しました。
中高校生の皆さんは、こんなわたしを反面教師にして、まじめに実技教科に取り組んでください。
中3生トップクラスの定期試験活用法 〜拾い物があるかも!〜 その1 2019/09/14
この季節は、「いずこも同じ 試験の夕暮れ」といった風です。
わたしの生徒さんもこの例に漏れず、です。
すでに試験の済んだ生徒さんもいれば、まだこれからという生徒さんもいます。
ところで、普段、トップクラスの生徒さんたちが集う塾では、「定期試験のための学習」ではなく、「受験指導」に焦点を当てています。
言い換えると、定期試験のような「狭い範囲」ではなく、入試のような「広い範囲」での学習に対応できるよう、カリキュラムを組んでいます。
そういう塾の場合、基本的に「普段の定期試験向け学習は、あなたたちが自力でやっておきなさい。塾はそこまで口出ししません」という姿勢です。
ただ、定期試験が近づくと、そうとばかりも言っていられません。
「テスト対策」と称して、各様の対策を行っています。
「内申評定」という「入試前の入試」があるからです。
しかし、トップクラスへのこうした「テスト対策」は、「内申評定のために、仕方なくやる」といった気持ちで取り組む受験関係者は、かなりいるのではないかと想像しています。
事実、受験関係者の方がお書きになるブログ等を拝読しますと、
「さっさと定期試験対策、終わって、入試問題、ガンガンやらせたい」
「定期試験のために、入試への歩みにブレーキがかかってしまう」
とお考えになっているのだろうということが、ほんとうによく伝わってきます。
わたしもこうした心情は、よく理解できます。
この点、ご父兄には、意外に感じられるかもしれません。
(次回に続きます)
中3生トップクラスの定期試験活用法 〜拾い物があるかも!〜 その2 2019/09/15
(前回の続きです)
中3生トップクラスの生徒さんたちも、この時期以降になると、頭の中は「入試一色」になります。
11月にある定期試験付近の頃を除くと、定期試験を顧みる余裕はなくなります。
そうした状況を考え、9月の定期試験が終わると、トップクラスの中3生には、「1年のときからの定期試験、解き直し」を指導しています。
だいたい、これをやろうとすると、彼らはイヤそうな顔をします(笑)
今さら、定期試験でもなかろうというわけです。
その表情を見て、わたしはこう彼らに言います。
「確かに、今さらあなたにとっては、定期試験でもないだろうと思います。
でも、理社は1年にやったことも、きっちり入試に出ていますよ。
それらをきっちり取りこぼしなくやれると言い切れますか?」
こういうと、だいたい彼らは、視線を下に落とします。
そして、「なるほど.....」といった表情をします。
これから先、入試の過去問、他県の入試問題、入試予想問題を、彼らはこなしていかねばなりません。
ですから、定期試験を顧みて、取りこぼしているところがないかどうかを確かめるのは、今の時期が最適だろうと考えるのです。
彼らは夏休みに、これまでの総ざらいをこなしています。
その定着がきちんとなされているかをチェックする際、定期試験の解き直しは、非常によくできた教材です。
(次回に続きます)
中3生トップクラスの定期試験活用法 〜拾い物があるかも!〜 その3 2019/09/16
(前回の続きです)
トップクラスの中3生の場合、「1年からの定期試験解き直し」と言っても、全科目全問ともやるわけではありません。
科目ごとに強弱があります。
英数については、試験当時に間違った問題だけをやります。
1問くらいは出る数学の難問は、十分に入試対策になります。
国語の読解については、初出と同じ感覚で取り組めます。
結構中身は忘れているでしょうから.....
理社については、全問解き直し、「満点を取れるかどうか」をチェックします。
やってみれば分かりますが、すべての科目で満点を取れるという人はまずいないでしょう。
何がしか、取りこぼしているものがあるはずです。
これをいかに拾い上げるかは、1点2点を競う上で、重要です。
しかも、定期試験の場合、入試では問われないような細かいこと、基本的なことまで問われたりすることが多いのです。
入試で解けない問題が出てきて、「実は過去に定期試験で問われてました」となれば、苦情の言いようがありません。
トップクラスの中3生に向けた定期試験対策を受験関係者から見れば、ともすると厄介者扱いしがちです。
定期試験向け学習を、できる限り入試対策に取り込めば、生徒さんたちの頑張りも生きます。
トップクラスの中3生としても、「1年からの定期試験の解き直し」に取り組むと、「思わぬ拾い物でラッキー!」となるかもです。
エフエムなとりラジオ番組に出演してきました 2019/09/17
去る9月7日付コラムおよび、ツイッターにて告知・レポートしておりましたとおり、昨日15日、エフエムなとり(通称なとらじ)のラジオ番組に出演してまいりました。
ラジオ番組に出演するというのは、初めてのことです。
そのため、放送局というのはどうなっているのか、興味津々でした。
なとらじの外観は↓の通りです。

雰囲気的に、以前は自動車の修理あるいは組み立て工場か何かだったのではないかと思います。
小ぢんまりとした雰囲気でした。
外には、なとらじの自動車がありました。

放送に入る前に、少々時間があり、スタッフの方といろいろな話をしました。
その際にいただいたパンフレットが↓です。
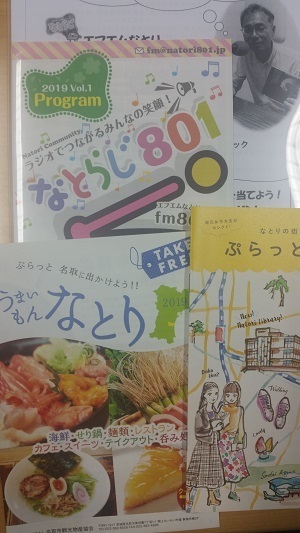
そうこうしているうちに、放送開始です。
赤間智美アナウンサーが担当する「なとらじwide」に生出演しました。
お話し申し上げた内容は、主として名取市に住む中学生を対象としたものです。
来春実施される公立高校入試の変更点、成績の上がる学習法、上手な塾・家庭教師の活用法などをお話しました。
番組のインターバルでは、わたしのリクエストで、河合奈保子さんの「スマイルフォーミー」をかけてもらいました。
これがとても、嬉しかったです(笑)

赤間アナウンサーは、とても語り口が柔らかです。

楽しい時間を過ごせました。
貴重な経験でした。
赤間アナウンサー、なとらじの皆様、そして、このたびの出演でお世話になった方々に改めて御礼申し上げます。

ありがとうございました。
「動画で雨か嵐か」 〜大学入試 指定校推薦の留意点〜 2019/09/18
宮城野区から見た多賀城高校・塩釜高校 その1 2019/09/18
先月、「塩釜・多賀城地区にとっての多賀城高校・塩釜高校 〜仙台からの受験生は優秀!〜」というコラムを書きました。
これは、塩釜・多賀城という視点から、多賀城高校や塩釜高校に入学する仙台からの受験生を見たものです。
わたしが多賀城出身ということもあり、どうしてもこういう視点になりがちです。
今回は、宮城野区から多賀城高校・塩釜高校を見た場合にどうかを書いてみます。
先般、宮城野中3年生の生徒さんと、進路全般について話していたとき、こんな話を聞きました。
.....友達の中で、偏差値40くらいの人が、親から「公立に行け」と言われて、塩釜高校を第一志望にしている。
この人だけでなく、ほかにも塩釜高校に行くって言っている人がいる。
これを聞いて、わたしは率直に「へ〜」と思いました。
わたしが前回のコラムで書いた数字の志向と通じるものがあったからです。
宮城野中辺りでも、塩釜高校はしっかり選択肢の中に入っているようです。
前回のコラムで、塩釜高校には、東仙台中出身者が50名、宮城野中出身者が10名在籍していると書きました。
また、塩釜一中出身者が59名、塩釜二中出身者が72名です。
東仙台中や宮城野中から塩釜高校までの通学距離を考えると、「かなりの数」といえます。
(次回に続きます)
宮城野区から見た多賀城高校・塩釜高校 その2 2019/09/19
(前回の続きです)
偏差値40くらいの受験生で、公立高校の普通科となれば、塩釜、宮城広瀬、泉松陵がターゲットでしょう。
あの辺の地区ですと、
◎宮城広瀬
→仙石線あるいは東北本線で仙台駅へ。そして仙山線で陸前落合まで。
◎泉松陵
→基本的に自家用車で送迎。片道30分程度。
◎塩釜高校
→仙石線または東北本線いずれでも乗り換えなしで通学可能
また東仙台中、宮城野中出身者が上記3校にどう進学しているかを示します。
数字の出典は、8月に書いたコラムの数字と同一です。
◎宮城広瀬
東:15 宮:21
◎泉松陵
東:4 宮:0
◎塩釜
東:50 宮:10
泉松陵は、意外なほどターゲットになっていません。
公共交通機関によるアクセスが難しいということがその理由なのでしょうか。
東仙台中出身者に関していうと、松島高校に在籍している人たちが、18名います。
宮城広瀬を上回る数字です。
松島高校なら、東北本線で東仙台駅から松島駅まで行けます。
さらに利府高校へも、同中からは17名が進んでいます。
利府高校ですと、東仙台駅から利府駅までのアクセスは可能です。
かなりきついですが、自転車という手もないわけではありません。
電動自転車だと、利府高校も「通学圏内」になり得ます。
東仙台中のターゲットの広さ、そしてJRというアクセスの大きさがここからも読み取れます。
(次回に続きます)
宮城野区から見た多賀城高校・塩釜高校 その3 2019/09/20
(前回の続きです)
前回までは、東仙台中を中心に、その動向を取り上げました。
宮城野区といっても、JRによるアクセスの有無、多賀城・利府に近いかどうかで、志向は変わってくるでしょう。
中野・高砂・田子・岩切といったところは、公立高校を考えるとき、仙台市中心部でなく、むしろ多賀城・塩釜・利府といったところに目が向いているようです。
あの周辺ですと、偏差値順に宮城野→多賀城→利府→塩釜となっています。
わたしがここで申し上げたいのは、宮城野原駅から西にある宮城野区で、偏差値40前後の公立高校を志向ということなら、塩釜へ目を向けている人たちが意外なほどいる、という事実の指摘です。
このくらいの成績の生徒さんですと、高校選びも「どこに行けばいいのか.....」といろいろと悩みが多いはずです。
「一応、現状はこうなっている」ということを参考にしていただければ幸いです。
ただ、個人的には、このクラスの生徒さんの場合、「私立高校を第一志望として選ぶ」という選択肢もあるのではないかと考えています。
ちょうど来年4月から、私立高校の実質無償化がスタートします。
「私立高校=公立より授業料がかかる」とは必ずしもならなくなります。
それゆえ、上記のような動向が数年後に少し違ってくるかもしれません。
発達障害を持つ生徒さんの高校受験 その1 2019/09/21
2016年8月に、「発達障害を持つ生徒さんの指導について」と題してコラムを書きました。
今回は、発達障害を持つ生徒さんの高校受験について記します。
そうした子息をお持ちのご父兄にとって、高校受験は、通常の場合より心配なはずです。
高校受験という側面を考えた場合、「発達障害」は、「学業不振」とともに語られることが多いように感じます。
これはこれで、真理の一面ではあります。
しかし、一口に「発達障害」といっても、事例は様々です。
必ずしも「発達障害」=「学業不振」とは限りません。
学業に特段問題はないが、行動面や他人とのコミュニケーションの際に、いろいろな困難があるという場合もあります。
実際、発達障害ということで引き受けた生徒さんの1人は、平均点を上回っていました。
5教科268点(146人中93位)まで下がったことがありましたが、390点(145人中47位)まで上がりました。
その生徒さんは、他と同じように試験を受け、高校に進学しています。
この生徒さん以外にも、「発達障害」と言われ、学習に特段の問題がなかった事例は、数件あります。
当該生徒さんの発達障害の内容がどういうものか、申告以上のことは聞けませんが、こういう生徒さんの場合、指導に支障はありません。
(次回に続きます)
発達障害を持つ生徒さんの高校受験 その2 2019/09/22
(前回の続きです)
そもそも、わたしは「発達障害」という言葉が適切なのかどうか、以前から疑問を感じています。
2012年の文科省の調査によると、「発達障害」の可能性があるとされた生徒の割合は次の通りです。
4.5%・・・学習面で著しい困難
3.6%・・・行動面で著しい困難
1.6%・・・学習面・行動面の両面で著しい困難
以上の数字は、実際に医師の診断を受けた数字ではありません。
学校の先生が見立てた数字です。
知的障害児が通学する支援学校の数字は除かれています。
以上の数字から見ると、約6.5%の生徒が「発達障害」ということになります。
この数字が正しければ、1クラスに2名くらいは「発達障害」に該当します。
わたしにとって、「障害」という言葉は、かなり重い響きがあります。
よって、これだけ「障害」という言葉を当てはめてしまうと、言葉の響きと相まって、いかがなものかと感じます。
「発達遅延」「発達遅滞」という言葉のほうが、現実に近い気がします。
(次回に続きます)
発達障害を持つ生徒さんの高校受験 その3 2019/09/23
(前回の続きです)
言葉の是非はともかくとして、「発達障害」の割合が6.5%というのは、多少納得できる部分があります。
「発達障害」という医師の診断を受けた生徒さんに接していると、「ああ。そういえば、こういう子って、昔、クラスにもいたっけな〜」と感じることがあります。
わたしが子供の時分は、「発達障害」ということが、現在ほど社会に認知されていませんでした。
「今にして思えば、彼や彼女.....は、発達障害って言われていたのかも.....」
と、思ったりもします。
わたしが思い当たる彼や彼女と、「発達障害」と言われた生徒さんでは、似ているところがたくさんあるからです。
わたしが何を言いたいのかというと、「発達障害」という言葉でくくられてはいても、それほど遠い存在ではないのだということです。
よって、高校受験の際も、通常の生徒さんと同様の試験を受け、高校に進学することになります。
特別措置は取られず、合否判定も通常の場合と同じです。
「発達障害」も、程度が重くなると、支援学校に行く必要のある場合が出てきます。
わたしも過去に1度だけ、支援学級に通う生徒さんの指導をしたことがあります。
しかし、こういうケースは全体を見ても、決して多くありません。
(次回に続きます)
発達障害を持つ生徒さんの高校受験 その4 2019/09/24
(前回の続きです)
わたしが「発達障害」の生徒さんに行うのは、「障害」を踏まえての受験指導です。
「障害」それ自体を軽減したりすることはできません。
それは、「発達障害」の専門家の仕事です。
逆にそうした専門家は、受験指導ができる訳ではありません。
ここでいう「受験指導」とは、学習を教えるだけではありません。
「この学校はこれくらいの点数を取っていれば入学できる」等のアドバイスができるかどうかを指します。
ですから、専門家によるカウンセリングと、わたしの受験指導とは、基本的に別物です。
そういう生徒さんを担当するときには、その生徒さんの現状を理解した上で、受験指導に臨んでいます。
「発達障害」が重度である場合、支援学校への進学も一つの選択肢になります。
ただし、そこまで重度というケースは少ないです。
そういう重度のケース以外の生徒さんが対象になるような、「発達障害専用の高校」というのはありません。
そういう生徒さんを専門に受け入れてくれるようなところがあれば、選択肢も増えるのですが.....
現在は、通常の全日制高校やサポート校という選択肢があるだけです。
また、卒業後においても、社会生活は他の人と同じ土俵の上で行います。
よって、他の生徒さんと同じように、受験情報には留意しておく必要があります。
それを手助けするのが、わたしの仕事です。
「動画で雨か嵐か」 〜二華中・青陵中 不合格となった後の進路〜 2019/09/25
二華中・青陵中受験の算数 我流にこだわる受験生の結果は..... その1 2019/09/25
先日行われた定期試験の数学で、計算のプロセスをすっ飛ばして、結果、計算間違いをした生徒さんに、「喝入れ」を行った旨、過般のツイッターで述べました。
きちんと計算を書けばいいものを、書かずに暗算で済ませて墓穴を掘るという生徒さんは、ホントにホントに多いです。
しかし、わたしとしては、これに妥協するわけには行きません。
手綱を緩めるつもりもありません。
数学つながりということで、今回話題にしたいのは、二華中・青陵中を志す生徒さんの算数に関してです。
わたしの指導の仕方というのは、「基本に忠実に」という一点につきます。
すなわち、
計算のプロセスはきちんと書く.....
暗算で計算しない.....
できる限り、図や表を書き、頭の中だけで考えない.....
ということです。
早い話が、「教科書通り」です。
わたしがこういう方法を推し進めているのは、結局のところ、最も確実に正解にたどり着くことができるからです。
また、わたし自身が、頭の中だけで考えて正解を導き出せるほど数学力が高くないという事情もあります。
一方で、わたしは生徒さんがいかに基本から外れた解き方をしていても、正解を出せている限り、それを認めています。
ただ、正解をしなければ、当然その生徒さんは、わたしから「教育的指導」を受けることになります。
(次回に続きます)
二華中・青陵中受験の算数 我流にこだわる受験生の結果は..... その2 2019/09/26
(前回の続きです)
しかしながら、不正解をして、わたしからの「教育的指導」を受けても、改めようとしない受験生が一定数います。
そうした受験生は、一般的に次のような特徴があります。
1.頭の回転は速いほう
2.計算のプロセスを書こうとせず、なるべく暗算で済まそうとする
3.問題を読んで考える際、図や表を書こうとしない
4.乱暴な解き方をした結果、誤答が散見される
5.指導者から解き方を矯正するよう指導を受けても、生返事だけで実行しようとしない
平均点に達しない小中学生を教えていると、上記のような生徒さんにはかなりの確率で遭遇します。
理由は、わたしの指導を受け入れるだけの能力が十分でないためです。
ゆえに、彼らは同じ間違いを同じように繰り返します。
ところが、もともと頭の回転が速く、能力的にはかなり高くても、上記のように我流に拘泥する受験生が意外なほどいるのには、正直申し上げてビックリしています。
彼らは平均的な生徒さんより、かなり能力的には高いです。
よって、わたしは彼らがいくら小学生とはいえ、それなりの合理的思考ができるはずなのではないかと考えていました。
しかし、現状はさにあらず。
いくら誤答を頻発しても、なお我流に拘泥するという現状が、どうしてもわたしには理解できません。
(次回に続きます)
二華中・青陵中受験の算数 我流にこだわる受験生の結果は..... その3 2019/09/27
(前回の続きです)
わたしは「その1」で述べたように、生徒さんが正解しているのなら、どのような解き方でも認めています。
一方、それが間違っているとあっては、当然に矯正しなくてはなりません。
ただ、矯正するに当たっては、「なぜそういう解法が必要か」「なぜそうしたほうがいいのか」を懇切丁寧に説明するようにしています。
わたしのやり方を問答無用で押し付けたくないからです。
しかし、そこまでしてなお、わたしの指摘事項を取り入れようとしないとなっては、「処置なし」です。
そういう傾向のある生徒さんから、
「問題、解けない..... 間違う.....」
「模擬試験の成績がダダ下がり.....」
と言われても、わたしの指導には限界があります。
当然のことながら、そうした生徒さんが二華中・青陵中に合格するほど、両校の入試は甘くありません。
まずは、わたしが「こうすると解けるようになるよ」「こうすれば、ミスが少なくなるよ」というのを、きちっと実践してもらう必要があります。
そうした生徒さんは、自分自身に根拠薄弱なプライドを持っているがゆえに、もともとの能力が高くない生徒さんより、よほど手に負えない感じがします。
(次回に続きます)
二華中・青陵中受験の算数 我流にこだわる受験生の結果は..... その4 2019/09/28
(前回の続きです)
今までわたしが担当した生徒さんの中には、二華中・青陵中の合格者がいます。
合格した生徒さんは、能力的に高いことは言うまでもありません。
加えて彼らは基本に忠実であり、かつわたしの指導することに聞く耳を持ってくれました。
「聞く耳を持った」というのは、指導の際にフンフンとうなずくだけではありません。
できる限りわたしの指導を取り入れてきたということです。
そうした生徒さんにとって、自分が何か特別なことをしたとは感じていないでしょう。
彼らは、二華中・青陵中への合格を願い、自然体でわたしの指導を実践してきました。
彼らが何か特別なことをしてきたかと言えば、全くそんなことはありません。
「当たり前のことを当たり前のようにしてきた」というだけです。
ところが、相応の能力はあるのに、指導されたことをちょっとでも実践してみようという気持ちがない受験生が一定数います。
これも性分なのだと言えばそれまでなのですが、残念なことです。
いつの日か、そういう性格は治るのかもしれません。
しかし、ハッキリしているのは、現在の彼らのような生徒さんを、二華中・青陵中は欲しがっていないということです。
この点、明確にしておきます。
9月29日現在の指導枠空き状況について 2019/09/29
本日現在の指導枠空き状況は以下の通りです。
お問い合わせをくださる方は、以下をご参照ください。
☆お問い合わせに当たって、合格実績を参考にしたいご父兄へ
当方の合格実績のページをご参照ください。
また、過去5年間の合格実績一覧もご参考にどうぞ。
<空き状況>
☆平日
火曜日夕方の早い時間17〜19時の枠が空くことになりました。
14時以前あるいは22時以降も受け付けております。
☆土曜・日曜
残り1〜2枠の空きがございます。
お住まいの場所の関係で、指導のできない場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。
☆9月以降の予定
9月は16日・23日が祝日です。
10月は新人戦に伴う振り替え休業、祝日、秋休みがあります。
その際の短期集中指導、追加指導も承ります。
10月の追加指導依頼もすでに承っております。
指導に当たって、当方は、特に次のような生徒さんの力になれます。
1.大学受験、赤点対策を希望する高校生
2.二華・青陵・附属など中学受験を予定する小学生
3.通塾しても、成績がなかなか上がらない中学生
☆学習障害やADHDなどの発達障害を持つ生徒さん、大歓迎!
9月は例年に比べて、動きが大きかったように思います。
ご家庭も夏休み、9月の定期試験を経て、いろいろとお考えになっているようです。
指導をお引き受けするに当たりましては、「生徒さんが、菊池の指導を受ける意思があること」のみを要件とします。
現状の成績については、一切問いません。
指導の際にかなり困難を伴う案件でも、生徒さんが菊池の指導を受ける意思がある限り、できる限りのことをいたします。
一方、「うちの子供は、全くやる気がありません。何とかやる気の出るようにして下さい」というご依頼は、申し訳ございませんが、力になれません。
引き続きよろしくお願いいたします。
手遅れとなる前にご相談・お問い合わせを 2019/09/30
今日は9月最終日となりました。
10月という声を聞くと、ご家庭でも「そろそろうちも新たな塾を」「家庭教師先はどういうところが?」という意識が随分と強くなり始めるころです。
受験関係者がお書きになるものを拝見しておりますと、どこでも、
「なるべく早めに来てください」
と、書いてあります。
まあ、ご家庭にしてみれば、「商売なんだからそうなんだろ」とお感じになるかもしれません。
もちろん、そういう側面が全くないとは言えません。
しかし、ビジネスとは関係なく、「早期発見、早期治療」「転ばぬ先の杖」ということが重要なのは言うまでもありません。
これは病気の治療と同じです。
相応の能力は持っているのに、任されるのが遅かったというケースはあります。
「もっと早く来てもらえれば、もっと成績アップできるのに..... もっと何とかなったのに.....」と地団駄を踏んでいる受験関係者は少なくありません。
家庭教師という指導体系の場合は、塾よりも動きがスローペースです。
「いよいよ切羽詰まって.....」という感じの「緊急搬送、緊急手術」を要する生徒さんが毎年来ます。
こうなると、できることはどうしても限られてしまいます。
あるご同業の方は、12月の終わりころに、偏差値37、平均評定3.1の中3生を持つご父兄から、「できれば二高、せめて三高に」と言われたご経験があるとか。
ここまで極端な例は少ないにしても、「もう少し早くいらしていただければ.....」というのは、毎年感じることです。
というわけで、「早め、早め」をよろしくお願いいたします。
ご利用案内 リンク
お気軽にお問合せください

メール・お電話でのお問合せ
<電話での受付>
15:00~20:00
※日曜日は除く
※電話は
「雅興産(みやびこうさん)」と出ます
成績upのヒント!
教育コラム「雨か嵐か」
プロ家庭教師菊池
住所
〒981-0933
仙台市青葉区柏木1-2-29-301
電話受付時間
15:00~20:00
定休日
日曜日

